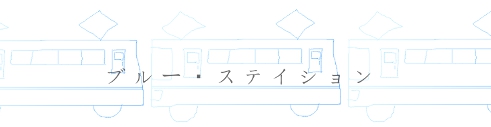 鉄道はデパートの最寄り駅を玄関にして、このあたりの集落を一巡する環状線が一本あるきりだ。車なんてぜいたく品を持てるのは一部の上層階級のひとたちだけで、だから集落をはなれるときはあの環状線に乗るのがだれにとってもふつうのことだった。 もっとも市は、たいていは集落ごとにちゃんと立っていたから日用品をそろえるのにそこをはなれる必要はない。たしかにデパートの前のそれがいっとう大きく立派ではあったけれど、別段、大きくあるべき理由もなかった。だから鉄道に乗ることがあるとしたらほんとうに”デパート”へ買い物にいくとき、それからデパートのちょうど真反対にある海側の中央駅へ向かうときくらいで、もちろんそうでないひともないわけではないけれど、そうであるひとのほうが一般的だった。 集落と集落の間はおどろくほど殺風景だ。数度の戦争で荒れ果てた、昔はこれほど過疎が進んではいなかったのだと、大人たち、こと高齢の老人たちはそろって口にしたが、ゆずこはこうなる前の風景をしらない。まばらに建つ小さな家々を見ると、なるほどたしかに寂しい気はしたけれど。 中央駅――セントラルには大きな学校がある。初等から高等までの学級を、校舎こそ分かれてはいるものの同一の敷地内にほうりこんだ、国営の学校だ。生徒の数は上級へあがるほど少なくなる。金銭的余裕がなければ教育を受け続けることはむずかしいし、必要性もそれほど説かれていない。高等学級までおさめればだいたいが国の最高基幹へその身をすすめた。そしてセントラルにはそれらの機関も身を寄せ合って群立している。そこは学生と、エリートの街なのだ。 さて、セントラルから一駅ずれると、海駅がある。海駅は、まさしく海だ。狭い人工浜の向こうに重たく黒ずんだ海面が、ときおり白綿のようなさざなみを巻きこんで揺れている。この海では魚も海藻類もほとんどとれない。泳ぐことすらむずかしく、レジャーに訪れる人もないにひとしい、ただそこにあるだけの海だ。昔はそうでもなかったのだと、これはまただれだか覚えてもいない老人のことば。人工浜がつくられる程度には海遊びは人々の求むるところだったという。けれどゆずこは――そしてたぶんこの男も同様に――そんなころの海をしらない。記憶のかぎり海はよごれて、黒いものだ。 がたたん、がたたん。かたい軌条の上をいくつもつらなった車体がはしる。学生や勤め人たちはとっくにそれぞれの城のなかだから、車内はうんと静かだった。 ゆずこは向かいに坐ってその長い足をゆったりと組んでいる男のすがたを見やった。ゆずこが大人の女なら、その足がじゃまで膝を抱えなければならないところだ。彼のおもてからはめずらしく愉しげな笑みがうすれていて、そういえばデパートの外で彼を見たことなど数えるほどしかなかったと、ゆずこはそれに気が付いた。気付かなくてよかったような気がする。 「中央駅へは行ったことがあるけど、わたし、海へいくのははじめて」 「うん」 男はちょっとおかしな返答をする。 「どうして海へ?」 「見たかったから」 へんなの、と、けれどそれを口にすることはできなかった。 海駅へは、デパート前駅からちょうど一時間ほど乗ればたどりつく。中央駅へはそこからものの五分で行くことができるが今日はそれを待たない。ほかのだれひとりも乗降しないひとつ手前の駅でふたりは降りた。 商人の足どりは妙だった。海へいきたいと言いだしたのは自分なのに、気乗りしない、というふうにふらふらと色んなものに立ちどまった。たとえば道ばたの、野良猫やなんかに。 とはいえ駅から海へは、それは海駅というだけあって、ほとんど距離もない。なれば当然、アトラクションとなりうるものもそうそう多くはなかった。ゆずこが商人の二歩前をゆくと、彼もしぶしぶあとをついてくる。海の波音がもう聞こえはじめていた。 車の通らない灰色の道路をわたり、ところどころが打ち破られたコンクリート堤防のむこうにあるなだらかなスロープをくだると、やはり知っているとおりの黒ずんだ砂浜があらわれた。 浜はたいした広さもない。猫の額のような窮屈さで、やはり黒ずんだ、よごれた波をだんまりと受けいれている。ざざん。ざざあん。その音はどこか高慢ちきな怪獣の呼吸のよう。どうだ、おそろしくて、近寄れないだろう。一歩でも入れば死んでしまうぞ! ふん、とゆずこは鼻をならした。言われなくったって、入らないよ。 「……なんだかこわいね」 つれない海にぶすったれたゆずこの横で商人は何も言おうとはしなかった。彼のかたい靴底が浜の粗礫を踏んでじゃり、と鳴った。ゆずこは商人を見上げてみる。へんなの、とゆずこはまた思った。 商人は海をじっと見ていた。南を向いた浜の水平線にはけぶるような灰色だけがある。曇り空とまじりあった海は色抜きの写真のようにぼんやりとしていてどこからが水なのかわからない。その、どこにあるのだかはっきりしない水面を瞳にうつしながら、けれど商人の目は鉱石のようにつやめいて濁らなかった。ざざん、ざざぁん……。 「ねえ商人さん、海を見たかったんだよね」 「ああ、見たかった」 言いながら、一歩、浜をすすんだ。浜には割れた貝殻や、原型のわからない錆びた金属が散乱している。いつ、だれが訪れて遺していったのか、あるいは潮に運ばれて打ち上げられたのか、由来のしれないたくさんの人工物と浜の砂礫は意外にもよく馴染んで、ところどころにヤドカリやカニが暮らしているらしい。商人はそれらには目もくれず、ただただどす黒い、重たい、海の水を見ている。 ゆずこはなんとなく退屈になって、仕方なく浜を自由に歩いた。ざくざく音を立てるたび足をとられそうになる。つっかけただけの粗末なサンダルと素足の隙間に海砂利が入りこんだ。そういえば、商人とゆずこの出で立ちは並べてみるとずいぶんちぐはぐだった。毛皮のロングコートに立派な軍靴で足元をかためた彼と、襟ぐりの伸びた赤茶色のシャツにホットパンツ、それからよごれたサンダルを履いただけのゆずこでは、どこかぜんぜんちがう場所に立ったふたりの合成写真だと言われたほうがよほどうなずける。もっとも、この海辺の気候にそぐわないのは商人のほうだと言えた。あつくないのかなあ、とゆずこは思う。そんなゆずこの視線にも、気づいていないのか放っているだけなのか、商人は興味を示さずただじっと、やはり空と海の境界を見ているのだった。 カタカタカタ。と、商人の腕が音を立てた気がした。潮風にふかれて、カタカタカタ。寒くてふるえているのだろうかと思えばどうもそうではないらしい、その腕はぴくりとも、動いてなんかいなかった。ゆずこはふいに不安になった。彼の腕は金属でできているから、海の風はあんまりよくないんじゃないかと思ったのだ。 「ゆずこ」 「なに」 呼ばれて、しゃがみかけた足をぐんと伸ばす。 「ゆずこ、おいで」 商人はようやくゆずこを見下ろすと、安っぽく鳴る金属の義手で手招きをした。なんだかあいまいに微笑んでいる。ゆずこはそれをすこしいぶかしんだけれど、おとなしく従うことにする。かけ寄ると、ゆずこという、子供の身体を彼は恋人にするようにぎゅうっと抱きしめた。 「どうしたの」 「なんでもねえよ。海が、見たかったんだ……」 うん、とゆずこはうなずいた。海が見たかったのだ。海はそこにある。けれど商人のまぶたは、妙につよく、かたく閉じられている。それからまた、海を見ていたのと同じくらいの時間、商人はほとんどじっと動こうとしなかった。 海を見たいと言った男の望みを、ゆずこはまるで正確に理解できなかった。けれどこうして抱きすくめられている己はいま、あなたの創造主、神様みたいだと思った。抱きしめる彼は敬虔な祈りの徒。 商人のふわふわのコートの向こうで、写真でしかみたことのなかった黒い海がたゆたっている。ざぶん、ざぶん、と鳴りながらこの信心深い男を連れていこうとしている。もしわたしが神様ならば彼のどんな願いを叶えてやるべきだろう。 よくわからなくて、ゆずこはぎゅっと、商人のかたい腕をなでさすった。 創造主は神様の力を使いすぎると、ぶわっと内側から錆が出て、この浜辺に打ち捨てられた金属のようにもう何にも、誰の役にも立てなくなって忘れられてしまうのだ。そうなるくらい強く、なにかの生成を願ってはいけない。商人の腕がどれほど冷え切っていても、それを願ってはいけないのだ。 浜辺の人工物はみな神様の屍体。それから、彼の四肢もおなじだ。 海の音に調子をあわせて、商人の腕は相変わらず、ふるえてないのに音が鳴ってる。 まだ応えないで、と。ゆずこは檻のように囲われた腕の中で、海風に全能を蝕まれるような不安とともに思った。まだ行かないで。まだ、消えてしまわないで。 海から駅へ戻るまでの間、ゆずこも商人も、言葉を口にしなかった。商人はゆずこの身体を大事そうに解放したあと、もうけっして、指一本触れようとはしなかった。ゆずこは急に寒くなった身体を自分の腕だけで抱いて、そこに血が通っている、ということをふかく認識していた。 無人の駅のプラットホームに、やはり乗客のほとんどいない軽々しい箱型の車両がすべりこんできて、ふたりを飲みこんだ。海はあっという間に遠ざかり、それから、信徒としての商人もまた、どこかへ消えたようだった。 ゆずこは来たときと同じように静かな列車の中で、ざぶん、ざぶぅん、という、あの呼び声のような音を思い出していた。 海へ行きたいと、彼は言ったのだ。 |