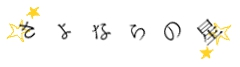 商人には学がない。 それはけしてめずらしいことではないけれど、さいわいにして初等教育を受けることのできているわたしにとって彼の無知は、とてもめずらしいことに思えた。わたしより圧倒的にこの世界のことをしっている彼は、しかしおどろくほど、この世界のことをしらないのだ。たしかに学がないというのは、そういうことにちがいないのだけれど。 デパートの外にいるときの彼は子供にかえったように小さくあどけなく、たよりなく見えることがあった。あの天をつらぬくかたい建造物を追われて、その外側に拡がっているのは彼の居場所などもうどこにもないような、荒れ果てた大地だけだ。その大地の上をあるく彼の姿はゆがんでかすんで今にも消えてしまいそう。ほしいものを手に入れたあとの彼は特にそうだ。そういうときの商人をみるのが、わたしはすこしきらいだった。 あるときわたしたちは星座の本を開いた。おかあさんにもらった古い本だったけれど、空にはそこへ描かれているものとおんなじ星星がかがやいている。そのことをもちろんわたしはしっている。 「ほら、あれがわし座のアルタイル。それからこと座のベガに、はくちょう座のデネブだよ」 わたしが指さした、夏の大三角やひしゃくの形を空に見つけたとき、彼はどこかきょとんとして、口を開いて天をみあげた。 「おまえ、ものをよく知っているんだなあ」 「そうかな?」 あなたがしらなさすぎるんだよ、とは言えるはずもない。言ったところで彼の自尊心を傷つけることは、ないかもしれない。それでも言いたくはなかった。わたしはしっているからだ。彼はそもそも、手に入らないとわかっているもののことなど、しろうとはしない。わたしにはいつも、それがすこしさびしい。共有することを拒まれているみたいだった。 「ねえ、さびしいっておもうことはないの?」 「なにが」 「ほしがること」 彼はまたきょとんとふしぎそうに首をかしげた。その首にさがっているたくさんの装飾品が星あかりにかがやく。きれいだと、純粋におもう。ほしいともたしかに。けれど。 「わたし、さびしいよ」 何を言っているのかわからない。彼はそういう顔をした。じっさいわたしはとても曖昧なことを言った。 なんだ、おまえ。そうやって突き放してもういちど星を見る。星はときおりまたたいて明度を変えた。遠い宇宙で燃えているそれを、わたしたちは永遠に手に入れられない。それどころか触れることも、朝になれば目で見ることすらできなくなるのだ。 「星、きれいだね」 「そうだなあ」 彼は簡単に言った。けれど欲しいとは、けして言わない。 ねがいごとはなに? 彼は彼自身のそれを、たぶん了解していない。 流れる星をみつけても、となえる言葉を持ちはしない。 もし彼があのデパートの何もかもを手に入れることがあったなら。 ああ、それはたぶん、とてもとてもさびしい日になる。 |