
「さく、髪ィ切ったろか」 午后。ふたりきりの事務所で、アザゼルが唐突に口を開いて告げた言葉は実に不可解だった。 初秋の乾きはじめた空気が肌に触れると寒々しく感ぜられるようになったので、りん子は先日から長袖のカーディガンを着用している。そのカーディガンの裾をちょいちょいと小さな手で引っ張る仕草がその時りん子を少しばかりおかしな気持ちにさせた。普段なら冷たくあしらってやるその者の存在に、ふと慈悲が湧いたのだ。 それは精悍な男の喉から発せられるような逞しく太い声ではあったが、実のところアザゼルはいま指すら満足に扱えぬ犬畜生の姿を取らされている。鋏など到底握れるとは思われないので、なるほど、とりん子は得心がいきデスクに向かっていた身体を半回転させた。それから伸ばしていた背をやんわりとたわませ、彼をのぞきこむように言う。 「駄目ですよ、そんなこと言って。結界は解きませんからね」 第一私じゃアクタベさんの結界は破れません。足元に立って、ようやくりん子の膝に及ぶかという小さな身体であるところのアザゼルはあからさまにしゅんと落ち込んで見せ、やはりそういう魂胆であったかとりん子は呆れた。彼は――いや、彼だけではない、悪魔たちは皆この窮屈で屈辱的な肉体の呪縛からどうにかして解放されようと日々あらゆる試行を怠らなかった。アザゼルときたら髪を切ってやるなど、随分と艶かしい言い訳を思いついたものだ。 「ちゃうねん、そんなつもりやない。ワシはたださくの髪を切ったりたいだけやねん」 「ハイハイありがとうございます、でも結構ですから、おとなしくしていてください。もうすぐこっちの作業も終わるんですから邪魔しないで」 「さく!」 掴まれたカーディガンをぐい、と強く引かれ、りん子はさすがに顔をしかめた。 「引っ張らないでください、伸びる」 地団駄を踏みそうな悔しげな表情で、アザゼルはりん子のカーディガンから手を離す。嬰児のようなてのひらをぎゅっと握り目に見えて震えるほどに強く結ぶアザゼルは、いつもより聞き分けがなく、いつもより頼りない、本当の子供になったような風情だった。 「もう」 りん子は再びチェアを回転させるとアザゼルの拳を両手ですくい、たった四本しかない指をひとつひとつ丁寧にほどいてやった。 「どうしたんですか、らしくない」 かたくなだったアザゼルの指は一本ごとにだんだんとゆるくなり、最後にはりん子にされるがまま、その手をおとなしく開いてみせた。けれどりん子の両手を離れるとそれらはだらんと力なく垂れ、その全身からは先程見えた悔しさよりもむしろ情けなさや挫折感のほうが強く感じとれた。本来の姿なら鋭く、触れたものを引き裂いてしまうその爪も、今はただ丸く、黒い小貝のように弱々しいのだった。 さく、とアザゼルは覚束なく呼んだ。それからりん子の両ふくらはぎをぬいぐるみにするようにぎゅうっと抱きしめると、そこへ顔をうずめ、動かなくなった。そのうえで「なあ、さくぅ……」などと、甘えた声を出すのである。 なんて、おそろしい。りん子は渋面をますますきつくした。 いつもならばこのような振る舞いを許したりはしない。けれどこの恐ろしく殊勝で頼りなげなアザゼルを常のごとく退けることは気が引けた。それではまるで幼児虐待だ。聞き分けがないだけで、実害を被っているわけでもなければ仕事の中断を指摘する上司も不在とくれば、りん子はこの悪魔に対してまっとうな暴力をふるえない。もしこれがアザゼルの作戦なのだとするならばそれもまたおそろしかった。何より今日までこの手段をとらなかったことに驚嘆を禁じ得ない。だがこれはそういう謀略の外にある、とりん子は感じた。おそらくアクタベが聞けば何を甘いことをと叱責をくれるだろうが。 「どうして髪なんか切りたいんです」 「どうしてもや」 「私、長さを変えるつもりはありませんよ」 「わかっとる。そんな切らへん、先っぽだけや」 「その言い方はちょっとなあ」 りん子の脚を抱いていた両腕をふと緩めると、アザゼルは懇願するように上目遣いにこちらを見た。可愛い顔とは言いがたかったが、妙に切実で、逼迫したものがある。本当にこの悪魔はいったいどうしたと言うのだろう。 「……わかりましたよ、他意がないことは信じます。でもどうしろって言うんです。その姿では鋏を握れないでしょう。私、変な頭になるのは嫌です」 「このビルを出たらええ。それからワシを喚びなおしてくれたら、結界も解けるやろ」 「あのねえ。この結界はあなたたちのためのものでもあるんですよ。天使に見つかったらどうするんです。たとえアザゼルさんだって、いなくなられたら困ります」 「そんなん! ワシが魔力を使わんかったらええハナシやろ!」 むっ、として、やや乱暴にアザゼルは喚いた。突然獰猛になった悪魔にりん子はわずかに怯む。それから少し腹立たしくなった。一体何だというのだ。だがそれで怒りに任せては悪魔たちの思うつぼだ。悪魔使いたるもの、これしきのことで立場を揺るがされてはならない。 りん子は短いため息を吐いてから、仕方ない、というふうに告げた。 「条件があります。まず喚びだしは私の部屋で行います。部屋を出ることは許しません。魔力も一切使わないでください。妙なことをすればすぐにお仕置きですからね。それと、」 「それと?」 「とっさに帰しても問題がないように、生贄は先に受け取ってください。何がいいんです、豚足? カレー? それとも他の、」 「髪がええ」 「は?」 「さくの、切り落とした髪をくれたらそれでええ。な、もうええやろ。ワシは一旦帰るし、ほんま頼むで」 そう言ったが早いか、アザゼルはあっという間に部屋を出ると、あの開かずの間へ駆け込んで自ら召喚陣の中へ沈んでいった。追いかけたりん子が扉を開けた時にはすでにアザゼルの姿はなく、ただしぃん、と耳の痛くなるような静寂だけがその場に滞っていた。 
グリモアに記されたアザゼルの陣はもうずいぶんと描きなれたもので、諳んじるとはいかないまでもほとんど時間をかけず正確に写し取れるくらいにはなって、りん子の手はすらすらと動いた。狭い部屋の真ん中に窮屈そうに描かれた陣はけれど、なお仰々しく、禍々しいもので、悪魔、という言葉を今一度反芻する。 「待ちくたびれたで。嘘、吐かれたかと思ったやん」 陣から這い上がるようにあらわれたアザゼルは出るなり不服そうに言った。身体は若い男のそれで、蹄のある変に曲がった両足と、露わになった上半身が神話めいてりん子の目に映りこんだ。同時に、逆立てた赤銅色の髪や獰猛な動物のような切れ上がった眦が、もし彼が人間ならば、という仮定をりん子に強請するのだった。 「残った仕事を片付けていたんです。終わらせなかったらアクタベさんに何言われるか」 「もうええよ。こうして、ここへ来られたんやから」 「……やっぱりなんだか変ですよ」 訝しむりん子に、ん、とだけアザゼルは応じた。 常ならばその姿を取り戻した彼は何をやらかすか察せぬほどに高揚し、暴れまわり、ついには数段グロテスクな方法で牽制されたものだったが、いまりん子の目前、描かれた丸い陣の上に座り込んだアザゼルは、ん、と短く言ったきり、人を不快にさせる言葉も態度も取ろうとはしない。触れようとしたり撫でようとしたり、それすら、ない。なんだか空恐ろしくなって、そのわずかな恐怖を払うように小さくかぶりを振った。 「……髪を、切ってくださるんですよね?」 「おお。切ったる。可愛くしたるで」 うなずいて、脇にあった新聞紙を床へ広げ敷く。アザゼルは新聞紙をひょいと避けるとようやく立ち上がり、その作業を真似て手伝った。 「なるべく髪の毛飛ばさないでくださいね、掃除が面倒ですから」 「気ィつけます」 りん子は自分の体が収まるように広げた新聞紙の中央へ風呂場の椅子を置きちょこんと座った。アザゼルは満足気にうなずいてりん子の背に回ると、妙にくすぐったくなる手つきで髪を梳きはじめる。彼がこれから切り落とされるわずかばかりの毛先を欲しがっているという事実にりん子は改めて言いようのない不理解を感じずにはいられなかった。 「これ、鋏です。それからこんなのしかなくって」 りん子はアザゼルに金属の華奢な鋏と、透明のプラスチック袋を手渡した。 「ジューブン、ジューブン」 アザゼルは大きな袋へシャキシャキと器用に鋏を入れた。それから「さくちゃん、目ェつむってー」と、子供をあやすように言うので、りん子は中途半端に目蓋を閉じた。頭を覆うように袋が被せられたかと思えば、スッとそれは首まで抜けて、すぐに呼吸が楽になる。ゴミ袋の合羽をまとって風呂椅子に腰掛ける自分はなんだか恰好がつかないと思いつつも、りん子はされるがまま、先ほどの警戒心が嘘のようにアザゼルを信用しきっていることに気がついた。そして今のところ、それが裏切られる気配はなかった。 「鋏いれまーす」 キンッ、と金属同士の触れあう高い音が耳のそばで鳴ったかと思うと、次の瞬間には毛の先が切り落とされていた。細かい針金が散らばり落ちるような、ばらついた、独特の音が半拍遅れて聞こえてくる。慎重に、幾度かそれを繰り返すと、アザゼルは調子をつかんだようにスイスイ鋏を動かした。 髪は丁寧にわずかずつ落とされた。房ごとぱさりと落ちたのは以前自らの手で前髪をととのえた折におかしくなっていたサイドを切られたときだけで、あとは筆の先より短い黒髪がそれぞれの望んだことのようにうつくしく舞い落ちるのみだった。その落葉は絶え間なくつづいたがしかしりん子の要請のとおりに鋏の刃からはあくまでもとの印象をくずさぬよう、そういう心づかいが伝わってきた。 「ねえアザゼルさん、どうして髪を切りたいなんて思ったんですか」 アザゼルが四本の指で器用に鋏を操るたび、ぱらら、ぱらら、という音が静かな部屋に響き渡った。りん子は断続的なそのリピートに息が詰まりだして、とうとう再び、それをたずねた。 答えてくれなくてもべつにいい。沈黙を紛らわせ、呼吸ではなく声を響かせるための単なる戯言だ。アザゼルが散髪に夢中になっていることはその息遣いからもよく感じられたし、その集中を乱すのも気が引けたが言わずにはおれなかった。髪を切りたいと駄々をこねる男などりん子の覚えているかぎりでは彼が初めてだった。 「なんちゅーかナァ……」 アザゼルは答えあぐね間延びした声をあげる。その間も両手は小気味良く動いた。りん子は答えを待つというわけでもなく何も言わないでおいた。その悩みかたがいっぱしの青年のような節とためらいをともなっていたので、なぜだかそれが心地よく、また照れくさくもあった。 「……これ、魔法やねん」 「は、」 と。しかし彼の声で告げられた言葉はりん子の想定を大きく外れていっそう不可解だった。「髪を切ってやる」と言ったその言葉以上に、である。 「マホウ?」 「そ。魔法や」 ジャキン。思い切りよく鋏が閉じられる。遠慮と躊躇がなくなって、彼の捌きは大胆である。 「さくちゃんが、どこにも連れてかれませんよーに、っちゅー魔法、まじない」 「はあ」 「あ、その声、信じてへんな?」 ……ジャキン。 アザゼルは鋏をとめて、脇からりん子をのぞきこむように屈み、責めた。りん子は思わずうっと息を止める。彼の微妙な体温が空気を媒介してかすかに伝わってきた。アザゼルの表情は真剣そのものである。 「まさかアザゼルさんの口から魔法なんて言葉が出てくるとは思わなくて」 「あんなあ、ワシ、悪魔やで?」 「悪魔だから、ですよ」 すくっと屈めていた身体を元に戻し、ふたたび鋏を動かしはじめたアザゼルは「うーん」とやや恥ずかしげに唸っている。恥ずかしげに! 今日の、この彼の反応はいちいち想定と食い違って調子が狂う、と考えながら、しかしそのリズミカルな刃物の音や動作に心地よさを覚えていることにりん子は気がついていた。 「悪魔は魔法を使われへんねん。こればっかりはどうにもならん。ワシ、淫奔やし」 「?」 「……役立たずやねん。ほんま。言わせんなやボケさく」 はあ、とうなずく。もはやりん子にはこのわけのわからない悪魔の悪態にいかる気すら起こらなかった。 ただ彼の望みがわからない。髪を切りたいと言ったことも、その髪を欲しがったことも、こうしてりん子を戸惑わせるだけの可愛げを未だに持てていたということも、すべてがすべて、りん子の思考や論理を乱暴に荒らして回るのだ。 アザゼルさん、と、理由もなく彼の名を呼んでみたくなったりなど、するのだ。 「せやからな、これはもう祈るしかないねん」 「祈る」 「そうや。ワシより偉くてごっつい悪魔にか、あるいは、にっくいにっくい神さんにか」 そう言ってアザゼルが天井を――もしかすると、天を――仰いだ気配がした。 「誰でもええ」 ジャキン。 突然背が寒くなる。髪を触るアザゼルの四本指が、なにか足りない、という感じをりん子に与えていた。窓から入る日がまろくなり、曇り昼はすこしずつ夕になる。不可解な焦燥が身の内から湧きおこってりん子は思わず顔をしかめた。 ……ジャキン、ジャキン、ジャキン! 
「ホイ、完成」 明るい声でアザゼルが言い、りん子はハッと目の醒めたような心地でうつむきかけの面を上げた。 「どしたん? ブサイクな顔して」 「殴りますよ」 「心配せんでも大丈夫やで、ちゃんときれいやし。ワシこういうのは得意やねん」 言うと、アザゼルはりん子の被っている袋を軽く叩いてその上に乗っていた細かい髪を払い落とした。彼がひとつ叩くたび、ばらら……、というあの音が鳴り、疎らになってついに聞こえなくなる。それからかぶせていた袋を鋏で切り裂くと、あっという間にりん子を解放した。 適当に放ってあった手鏡を拾い上げ、覗きこめば見慣れた己の顔がある。特別きれいということもなければ二目と見れぬ醜女でもない。つまらない、とりとめのない、平凡で人の記憶に残らない顔だと思う。 「あんまり変わってませんね」 「アホ! ちゃんと見ぃ、あっとーてきに可愛くなっとるやないか」 アザゼルはりん子の手から乱暴に奪った鏡を押しつけるように寄せてくる。そうは言ってもそこにあるのは何の変哲もない佐隈りん子の顔だ。アア素敵、魔法みたい! などと、今更思われるはずがない。鏡面が頬に触れそうになって、りん子は思わずやめてください、と呻いていた。 「……普通、ですよ」 ため息を吐いてしまいたいのをかろうじてこらえ、冷めて聞こえるようにりん子は言い放った。凡庸であることを嘆けるほどに自分は幼くも熱心でもないし、矜持だってある。それに、自己卑下は弱さだと芥辺には教わった。自信がなければないだけ、人は悪魔につけこまれると。 つまらなそうに言うりん子を、ふん、と、アザゼルが鼻で笑った。 「そうやで。フツーや。おぼこいふりして金にがめつかろうが男惑わしとろうが、悪魔使役しとろうがな、さくちゃんはナンも特別やあらへん」 「、どうせ」 「さくは人間やな。アッタリマエの、人間や」 唾を飲んだ瞬間に髪の隙間へアザゼルの指が通ったので、りん子はつかの間動けなくなった。他人の仕草そのものに、生まれて初めていつくしみを感じ取った。 それをもたらしたのが悪魔だなどと皮肉なこともあるものだ。思わずにはいられないが、そうして一笑に付せるほど、自分はまだ美しくなれていない。唖になったようにりん子は言語を失った。 「かわええよ、さく。ワシは人間が大好きや」 アザゼルはなおもりん子の髪を梳き、撫でている。水の流れをゆがめる仕草。悪魔の手のひらは沈められるだけで人をこうも惑わせるのだ。甘い言葉を吐き、誘い、揺るがし、過たせるのだ。悪魔というのはそういうものだと、それは人間ならば誰だってちゃんと知っている。知らないのはきっと悪魔使いだけだ。自分たちだけがそれを、本当には理解していない。だから、彼らを使役などできてしまうのだろう。 「どうして、」 髪なんか。それは魔法だとアザゼルは言った。では、その願い事は何だろう。さくが、どこへも連れていかれませんように。それと同じ言葉をずっと昔にも聞いた気がする。私はどこへゆくのだろう。誰に連れて、ゆかれるのだろう。 「ん、」 アザゼルが恭しく頭を下げるような動きかたでりん子の傍らにしゃがみこんだ。わけのわからない慈しみをたたえた横顔が、床に敷かれた新聞紙を丁寧にまとめ、その上にいくらか乗っていた髪を一処に集める。りん子はそれを気味の悪い生き物のように感じ、固くなって見下ろした。 散髪が魔法なら切り落とされた髪は呪いのかたしろだ。それを悪魔に持ってゆかれることに、抵抗ならいくらでもあった。よくないことが起こるのではないか。そういう危惧も今ではできるようになってきた。学習、したのだ。それだのにアザゼルの裸の背を押し黙ったまま見下げて、得も言われぬ焦燥を抱く己はなんだろう。 「ほな」 一枚の新聞紙だけを拾い上げ、あとは捻ってゴミ箱に捨てると、アザゼルはりん子を一瞥した。小脇に抱えられたそれをやはりりん子はジッと見た。 「ワシは帰るで」 いっそ別の思惑がアザゼルにあってくれれば良かった。適当に整頓されたりん子の部屋にいかにも不似合いな異形の悪魔が当たり前に別れ際の台詞を吐いた。しゅんかん、暮れなずんでいた日が意を決しあっという間に落ちたように、室内はにわかに暗さを増す。その毛髪をどうするのだとりん子はとうとう聞けなかった。 消さずに残しておいた陣の上へアザゼルは蹄の脚で立つ。その姿は一枚のタロットカードのように完成されている。アザゼルの存在をさとり、陣がほのかに光ると、アザゼルの身体もまたその光を帯びはじめる。 「ああ、せや」 青白く発光するアザゼルは、陣が液体のように彼を呑みこむまぎわ決まり悪そうにりん子を振り返った。 「あンな……」 頬をかきながら、今にも消えようというわりにのんきな物言いでりん子を窺った。どうしたのだともはや聞く気にもなれず、続く言葉を待つ。そうしたりん子の気配を察してかアザゼルはピンと背を伸ばしてその節くれだった指をのばした。それからわずかだけ短くなったりん子の髪に触れ、もてあそぶように二三度ゆらしてみせる。くすぐったく、りん子は首をすくめた。彼はその仕草をちいさくわらい、そして。 「――」 耳元でささやくと、ふ、とアザゼルの姿は霧のように消えてしまった。 「……なに、」 雲への照り映えにたよって明るんでいる部屋でりん子は茫然と立ち尽くしている。アザゼルの落としていった言葉の意味をはかりかね、足裏でわずかにこぼれたらしい髪のきれはしを踏んだ。陣はもはや光らずただ沈黙を守っている。悪魔たちへつながる円形のそれは、いつか己を呑みこむかもしれないと、りん子はいつだって考えていた。 ……ちゃぁんと抵抗、するんやで…… ゆびさきがかすかにふるえた。ととのった毛先に手をやり、確かめる。うしなわれたそこから先はもうここにはない。髪を梳くあのするどい指先が、すべて持っていってしまった。 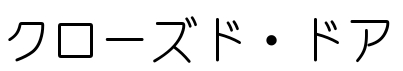 |