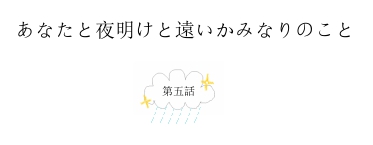 クリーム色のカーテンが弱い空調の風にたゆたうように揺れている。目蓋を開いてすこし顔を傾けると雫がこぼれ、つたった頬にひりっと沁みた。 あの強かった雨脚はいつの間にか弱まって空宙には霧のような水が浮かぶ。雲の動きもはっきりと見て取れた。よどみ、こごり、街の色彩を暗くしていた雨雲はいつのまにか散り散りになって薄れその向こう側から白い太陽が見え隠れしていた。長い眠りから目覚めるようにそれは徐ろに明るさを取り戻す。もうじきに雨は上がるだろう。濡れたビルとビルのあいだからその黎明の気配がする。 りん子は覚醒しきらないまま痛む右頬に手を伸ばした。 そうしようとして自分がどこか見知らぬ場所のベッドの上に横たわっていると、今ようやくそれに気がつく。白く清潔なシーツはきっちりとりん子の肩までをおおい乱れることなくととのえられていた。りん子ははて、と首を傾げる。なぜ眠っていたのだろう。ここは、どこだろう。 「目が覚めたか」 呆然としていると唐突に声をかけられ、驚いた。しかしその驚きに見合うほどりん子は大きく動くことが出来なかった。代わりに目をみはり、ベッドの右横の丸椅子に腰掛けてちょっと背を丸め、腕を組んでいたその人のことを凝っと見る。 「アクタベ、さん?」 そう呼びかけたずねると彼はわずかに目を細くした。どうということもなかったが、それはどこかくすぐったくなるような動作だった。 「あの、私」 「痛むか」 「え? と……ほっぺたは、ちょっと痛いです」 問われた言葉に訳もわからず答えるが、それは今りん子の知りたいこととは違っていた。芥辺は短くほとんど聞こえないほどの小さいため息をついて、それから長い仕事のあとでそうするように、目蓋ごしに眼球を揉む。 「あの、ここは」 「病院だ。覚えていないか?」 どうやら身体中がかたくなっているらしい。芥辺は今度は肩をほぐすように動かし、そうしたあとで膝に肘をついてりん子の顔を覗きこんだ。 「殴られただろう、思いきり。まだ少し腫れてる」 「えっ?」 「ほら、そこ」 ちょんっと右頬にふれられると痺れるように痛みが走った。りん子は短く悲鳴をあげる。殴られた、というより擦り傷のような痛み方だった。しかしその電気的な痛みのおかげか、りん子はようやく事の顛末を思い出しアッと身体を起こしかける。 「千春ちゃんは?」 「別の部屋で点滴を受けている。特に外傷はなかったが、丸一日飲まず食わずだったらしいな」 「……よかった。無事だったんですね」 芥辺は小さくうなずいた。りん子はずるずると脱力してふたたび柔らかなベッドの上に身を倒す。 「今、何時ですか」 「四時ちょうど。君が眠っていたのはほんの二時間ほどだ」 「アクタベさん、ずっと付いててくださったんですか」 「ずっとじゃない。あの変態野郎を警察にお届けしてから、ついさっき来たところ」 「ああ。警察……やっと動いてくれたんですね」 「監禁罪に傷害罪。やつは立派な犯罪者だからな。再起不能とまではいかないかもしれないが、まあしばらくは自由が利かないだろうし、たとえ実刑にならなくてもあの法律事務所は即刻クビだろう」 「そう、ですか。でもアクタベさん、警察なんて行っていたわりに随分はやく戻って来られましたね」 「これから何度か聴取はされるだろう。俺は当事者ではないから、今日は帰してもらったんだ。それに当の被害者にしたってあの状態だし」 「なるほど」 ひねっていた首がつかれてくるので、りん子は芥辺に向けていた視線を天井へうつした。 天井にはどういう由来でついたものなのか、てのひら大の茶色い染みがある。その近くを線路のように走るカーテンレールにはあまったフックがいくつか寂しげに垂れていた。 病室は五六人を収容することのできる大きな部屋であるらしかったが、窓際のベッドで眠っていたりん子はこの部屋にあと何人の傷病人がおるのかを知らない。けれどそのひとりの気配も感じられぬほど室内は静謐にみちていた。 「……」 身体中を倦怠感がおおっている。芥辺が腫れていると断じた右頬はしかし触れたり動かしたりしなければ痛みなど気づかないくらいに大した怪我でもない。ないはずなのに、なぜか起き上がるのが億劫だった。布団に触れた背中にはわずかに汗が滲みまさに夕方のうたた寝から目覚めたときのような感覚だ。 その気だるさのなか、うろ覚えながら事の顛末をなんとなく思い出した。そうだ、この人が、助けに来てくれたのだった……。 横から顔面を殴られて混濁しかけた意識の中で、たしかに芥辺の声を聞いた。さくまさん、と。あんなにも声を張り上げて名を呼ばれたのは初めてだった。ああ来てくれた。そう思った瞬間に、それはほとんど安堵のために、りん子は意識を手放したのだった。 「さくまさん」 曖昧な回想に耽って黙りこんだりん子に向かって、芥辺は呼ぶ。もう幾度となく呼ばれてきたそのまろやかな発音に今更ながらりん子は驚いた。こんなにもやさしげに、人を呼ぶことのできる人だったか。 「なん、ですか」 いま、その穏やかさが、妙におそろしい。怒っているのだとすぐにわかった。おそるおそる視線をやって、りん子の身体は肉食獣に睨まれた小動物のように硬直する。 芥辺の瞳は、本当に、ぞっとするほど暗かった。 「俺は、言ったはずだよな」 「……な、」 「関わるなと。何度も、そう」 腰掛けていた丸椅子から立ち上がり芥辺はベッドの傍らからじっとりん子を見下ろす。ゆら、と、あのとき――りん子が三崎と食事をしたことを報告したときと同じように、黒いものが目に見えて漂った気がする。そんなはずはないと首を振りたかったが、身体が思うように動かなかった。 「なあ、どうするつもりだったんだ?」 彼はゆっくりゆっくり、身体をかがめた。沈んでいく太陽のようにためらいがちに彼の瞳が近づいてくる。穏やかな言葉調に反して、今にもその指がりん子を縊り殺してしまいそうな、思いつめた目をしている。 「どうするつもりだったんだ、さくまさん。俺があのとき君を見つけなかったら。神に祈れば助かるとでも思っていたのか」 「ちが、」 ガン! と身体に衝撃が走ったかと思うと、彼は今にもりん子を押しつぶしそうなほど近くまで迫っていた。りん子の顔の両脇に手をついて動きを封じると、暗く、深く、底の知れない沼端のような瞳がりん子を見下ろしていた。 「君を見ていると苛々する」 雲の向こうのゆるやかな日が、今は大きな身体に遮られて見えなかった。でも遮っている彼にもきっとそれは見えていない。光を失ったふたりは両者の間にある暗がりだけをじっと見ている。 「いないんだよ、さくまさん」 静かな声で芥辺は言う。りん子は恐怖よりも、その声の波立たなさに、心臓をつぶされるような思いだった。 「君を救ってくれる、神様なんてどこにもいない」 芥辺のいいはなった言葉は、白い闇にただよいつづける悪夢のような響きを持っていた。神などいない。はじめからいない。それともいなくなってしまったのか。今にも泣き出しそうなのは、けれど、どちらのほうだろう? 本当に絶望しているのは、この悲しみに、殺されそうなのは。 ――神など、いない。 長い長い沈黙がうまれた。芥辺もりん子も、身を捩ることすらしなかった。 雨はまだやまない。さあさあと、沢の清流のような涼やかな水がまだ舞っている。すごくすごく遠くで獣の喉鳴りに似た雷の音が聞こえているが、それは徐々に徐々に聞こえづらくなった。 肩越しに見える白天井が、彼を黒く塗りつぶしているみたいだとりん子は思った。りん子の顔の脇に手をついた芥辺は今にも覆いかぶさってきそうなくらいに近く、大きい。けれども彼はりん子を見下ろした恰好のままじっと動かなかった。 あと少しなのだ。あと少しで、雨はやむ。雷も聞こえなくなって雲が途切れる。そうしたらきっと、その向こうから夜明けのような雨上がりがやってくるだろう。 覚えている。忘れていない。そうだ、前にもこうして。 このおおきな影に遮られた、ひかりの中で呼吸をしたことがある。  気丈な質である母の泣き顔を見たのは、後にも先にもこの時だけだ。 それくらい彼女にとって”これ”はショックだったのだろうし、悲しくゆるしがたい出来事だったのだろう。そしてそのことはりん子にとってもまたひどく悲劇的で、衝撃的で、許されることはないのだと強く感じた。 ダイニングのテーブルに肘をつきあの大きな手のひらで顔面を覆った母は、その顔が見えずともわかるくらいハッキリと泣いている。流れる川の濁流のように轟々と、それは苛烈で、陰気で、近付くものを呑みこんでいくような暗い悲しみだった。 私がもっと、きつく言わねばならなかったのだ。号泣の中で彼女が一番にくり返したのはそのことだった。足りなかった。届かなかった。聞こえていなかった。時にそれは悲しみを凌駕するほどの怒りを孕んで発せられる。彼女はひどく、後悔していた。 ほとんど呻くように泣き続ける母の傍らにはいつも酒があった。彼女の顎を伝い、テーブルにこぼれ、部屋中に強いにおいを放ちながら、それは彼女の感情を紛らわせていたのかもしれない。母は飲むことをやめなかった。憐れむ目をした父が彼女の肩を撫でても彼女は決して癒されなかったが、その傷薬のようなにおいのする酒を煽っているときだけ、彼女はうつろな目をして泣き声をしずめた。 りん子はその様子をいつも、自室のドアをうすく開いてじっと見ていた。伝播してくる悲しみと憎悪が、あるいは自分に向けられているのかもしれないことをりん子は悟っていた。それでも見ることをやめなかった、やめられなかった。 おかあさんが、ないている。 泣いているのだ。それも多分、自分のせいで。 母がりん子をその場所に連れてきたのは、救われぬ母娘としての、藁にもすがる思いだったのかもしれないし、あるいは単に自身を責めることに疲れきっただけだったのかもしれない。本当のところは今となっては知ることはできないが、とにかく母はその扉を叩いた。表通りから隔絶された暗い場所にそれはあり、見るからに怪しく、胡散臭いところだと幼心に思ったものだ。 開かれたドアの向こうから現れたのはひとことでいえば、まっくろのひと、だった。彼をあらわす言葉はそれ以上にはひとつだって存在しないように思われた。怖いとも違う。悪いとも違う。暗いとも強いとも違って、とにかく彼はくろい人だった。 母とりん子は部屋の中央にある簡素なソファに座るようすすめられ、母にはアイスティーが、りん子にはオレンジジュースがそれぞれ出された。 ごようけんは、とその人は言った。抑揚のない声で、けれども母をしっかりと見据えながら。母は怯みもせずに――こういうところが、母とりん子はよく似ている――ただ救ってほしいのだと訴えた。あのおぞましい出来事をなるべく大雑把にかいつまんで伝え、どんな方法でもかまわわない、とにかく救ってほしいのだと、最後には感情を抑えきれぬように昂ぶって腰を浮かせていた。 母の話を聞きおえると男はひとめ、りん子を見た。りん子はそのまっすぐな視線に身体を動かせなくなる。空間が次元をとびこえたようにしん、として、ひどく緊張する。男はふっとまたたきをするとそれからふたたび母に向きなおり、方法はありますと、そう低く言った。 「残念ながらウチは殺し屋じゃないんでね。相手の男を抹殺するだとかそういったことは行いかねますが、まあどの道そんな方法ではなんの解決にもならないでしょう。ならその子をどうにかするしかない。胡散臭いのを承知で言わせていただきますと、そう、記憶を消去することは、不可能ではありません」 「記憶を?」 「なんならあなたの記憶もまとめて。その娘さんが……暴行されたそのときの記憶をすっかり全部消すことができます。記憶というのは、ある意味で事実そのものにとても近い。忘れてしまえばそれは当人にとってなかったことと同じです。その忘却が周囲の人間にまで及ぶなら、もはやその事実は存在しなくなる。無論今回の件を知るすべての人間を集めることは難しいでしょうし、それはあまり現実的な話ではありませんが」 どうします、と男は迫った。静かで、整っていて、地の底からはいあがってくるような声だった。 母はむっとだまりこんだ。記憶を、ともう一度反芻してうつむくとしばらく動かなくなる。そんな母の様子を横目に見ながら、りん子はほとんど理解も出来ない、しようとも思えない、母と男の会話を音楽のように聴きつづけた。それから空調の効いた室内の風のささやかさとジュースの喉にしみる感じと、それだけをひたすらに思っていた。 「……お願いします」 だから母が、沈黙を破って厳かにそういったときには嗚呼、と短く感嘆するだけで何も言うことは出来なかった。りん子はその断罪のような声を聞いた。ついに許されることはなかったのだと、そう思いながら。 「そうですか……分かりました。承りましょう。ただし、記憶の消去はここでは行えません。とある山中の寺まで行く必要があります。そしてその寺の名前や所在をあなたがたに明かすことはできません。もしも娘さんの記憶だけを消去することをお望みならば、この子の身柄を一時的にお預かりすることになります」 「そ、そんな……」 「ご心配でしょうね。娘さん――それも、こんな目に遭ったばかりの幼い子を目の届かぬところへ連れてゆかれるのですから。何故名を知らせてもらえないのか、場所を明かしてもらえないのか、疑問はごもっともです。しかしこれは記憶の消去を行うことの最低限の条件です。ご承服いただけなければ今回の依頼はお断りすることになります。私はどちらでも構いませんので、どうぞ、お選びください」 淡々と言うこの男はむしろ、正直なところ依頼を受けることを快く思っていないのかもしれないとりん子は思った。母を見る男の目にはどこか侮蔑のような色が滲んでいる。金を積んで依頼をしようという顧客に対する態度とはとても思えない。 それなのに、時折りん子へちらりと与えられるまなざしにあるのは悲しみのようである。哀しみのようで、憐れみのようで、もっと言えば慈しみのようですらあった。そのまなざしに動きを制されたように感じながら、どうしてだろう、と考える。どうしてこんな目をして、わたしを見るのだろう。 「……ええ、分かりました。どうか、お願いします。かならずりん子を無事に返してくださいね、必ず、必ずですよ」 「それはお約束しましょう。では、こちらにサインを」 男は母にいくつかの書類を差し出した。母はすらすらとそこに名を記してゆく。そのなめらかな手の動きからりん子は目を離すことができなかった。 「後ほど一日分の着替えを持ってきていただけますか。寺から戻ったらすぐご連絡いたします。明日中には片付くと思いますので、そうしたらこの子を迎えに、またこの場所へ来て下さい」 「はい、分かりました。りん子、この人の言う事をよく聞いてね。すぐに迎えにくるからね、それまで迷惑かけないように、いい子にしてるのよ」 「おかあさん?」 「ちょっとの間だけ、おかあさんとはおわかれよ。でも心配しないで。これはあなたの為なんだから」 母の目には涙が浮かんでいた。こぼれたり、頬をつたったりすることはなかったが、それはきらきらと彼女のまなじりで耐えるように光った。 「いい子ね、りん子……悲しいことなんか全部忘れちゃいましょう。怖いことなんか、何にもなかったわ……」 ぎゅっと抱きすくめられて、母のそれが伝わってきたのかもしれない。りん子は突然泣きたくなって、でも今ここで泣くことは許されないような気がして、目を閉じた。 「はい、おかあさん」 答えると、母の腕にぎゅうっと力がこもった。 ……はい、おかあさん……。 いい子にしています。迷惑かけません。この人のいうことをきいて、おとなしくしています。だからはやく、むかえにきてください。 それらの言葉を飲みこんでりん子はもう一度、さっきよりもずっと頼りない声で、 「はい、おかあさん……」 と呟いた。  次の日はやくに、りん子は男に連れられて事務所を出た。 まだ人影もまばらな朝の街はそれでもすでにじっと暑く駅にたどりつく前にりん子の背中は汗ばんでいた。 駅にはスーツ姿のサラリーマンや制服を着た学生の姿がちらほら見られ、その中にはりん子と男のほうを見てはぎょっとしたような顔をする人もいた。どうやらふたりは傍目には異様な組み合わせに見えるらしいのだ。背中のリュックサックを負いなおして男を見上げると、けれど彼はさして気にしたふうもなく涼しい顔をしていた。 彼は慣れた様子で自動券売機に向かい、切符を買うと「こども」と書かれた一枚をりん子に手渡した。それを持って改札をくぐり、長い迷路のような通路と階段とを何度も上がったり下がったりし、ふたりはようやくほとんど人気のないそのプラットフォームにたどりついた。 それは巨大な駅のいちばん端っこにあった。屋外のホームには空調設備もなく、雑草の生える線路は陽炎に揺れている。周りを見回してもそこにはりん子たちのほかにほとんど誰もいない。反対方向の電車を待つ腰の曲がった老人がひとり認められるだけだ。 男はりん子にそこで待つように言うと自分はすたすたとどこかへいってしまった。りん子は背負っていたリュックを足元に下ろす。ひらけたホームにひとりで立っていると妙に不安で、男が消えていった方向をにらむように見つめた。 線路の向こうには金網があって、そのさらに向こうにはどこかで見たことのあるような工事道具や、線路のパーツのようなものが積んであった。干し草のような色をした芝生が拡がるそこがまるでまったく見も知らぬ荒野のように思え、りん子は途方にくれてうつむき、それからぐっと汗を拭う。風はなく、停滞した空気はどこか煤けていきぐるしい。 「わっ」 いつの間にかもどってきていた男が背後に立っていたのでりん子は思わず声をあげる。彼はどうにも、気配を消して動くことに慣れすぎているらしい。 「持て」 「は、はい」 男の手には白いビニル袋が提げられ、その中にはペットボトルの飲み物や、パンや、おにぎりなどがいくつも入っていた。その袋ごと手渡されて受けとると男は代わりというようにりん子のリュックサックを肩にかつぐ。ちょうどそこへ滑りこんできたたった二両だけの電車にふたりは乗りこんだ。 車中は冷房が効いていてりん子はようやく生き返った気がした。電車は数えるほどしか見たことのない、いわゆるボックスシートというやつが並んでいて、ちょっぴり感動する。始発電車であるらしく中に人の姿はない。がらがらの車内で適当に選んだシートに男と向かいあって腰かけるとまるで遠足のような気分で、楽しかった。 「食べてもいいですか」 先ほど手渡されたたくさんの食料を両手で衒ってみせて、りん子は男にたずねた。実を言えば朝からなにも口にしていない。そろそろぎゅるぎゅると腹の虫が鳴りだしそうだった。 「コーヒー、とって」 男に言われるままりん子は袋をあさり、そこから冷えた缶コーヒーを取りだす。それを受けとると男は足を組んで窓際に肘をついた。 「あとはいい。好きに食べろ」 ちょうどそのときゆっくりと列車が動き出す。ホームを抜け、遠ざかってゆく駅を窓の外に見送りながら、これからどこにいくのだろうとりん子はぼんやり考えた。カタタン、カタタン、と車両がリズムよく揺れだす。そうだ思いきって聞いてみようと身を乗りだしたが、タイミング悪く彼は持ってきていたらしい本を開いて読みはじめてしまう。出端をくじかれ何となく情けない気持ちになってりん子はおとなしく袋の中身をのぞいた。 袋の中にはたくさんの、本当にたくさんの食べ物がつめこまれていた。目につくかぎりすべて買いこんだというかんじで、この短時間によくもまあここまで揃えたものだと感心するくらいだった。 「これ、たべます」 りん子はその中からたらこのおにぎりを選んでてのひらに乗せた。男は本から目を離すとちょっと眉間に皺を寄せ、ああ、とそっけなく返す。 パリパリと包装を剥いて器用に海苔を巻きつけるとあたりにぷぅんとにおいが漂った。男は開いた本のページを口元に当ててまだりん子を見ている。その視線に気づきながらも応えることはしないでおにぎりにかじりつく。パリっと海苔の割れる音がして、今日はじめて口にするたべもののおいしさにりん子はほうっと気の抜けるような息を吐いた。 パリパリ、むしゃむしゃ、カタタンカタタン。パリパリ、むしゃむしゃ、カタタンカタタン。 咀嚼する音が車内に響く。その合間に線路のつぎめを乗りこえるかたい音も聞こえて、あ、遠くへ行くんだとりん子は思った。 男はようやく満足したらしくりん子から目を離すとふたたび読書に没頭する。そこでようやくりん子も彼を見、一点の曇りもない澄んだ黒さをじっと観察した。 彼の読んでいるのはタイトルの振られていない古く分厚い本で、金色の箔を押した表紙からそれが物語なのかむずかしい学術書なのかはたまた単なる日記だったりするのか、推し量ることは出来ない。文字を追っている瞳の動きから横書きの何かが書かれているらしいことは分かるのだが、虹彩を除いて彼の表情はぴくりとも動かないので、やはりその内容は想像することすらむずかしかった。 りん子はぷいと窓の外を見やる。驚くほどあっという間に都会の景色は遠ざかって、辺りは稲苗の緑や畑土の茶色や、空の青さなどが延々続いていた。二両編成の小さな列車はしかし意外にもしっかりとしたスピードでその風景を切りめぐる。電線の流れかたがぐんぐんと速くなり、きっとこの窓をあけたら強い風がふいてくるに違いないと、それを想像した。 ――こんな開放的な気持ちは久しぶりだ。りん子は思った。 これから向かう先がしれなくて不安に思っていたのが嘘のように、そこには切ないくらいの行きたい! があふれていた。私は遠くへ行くんだ、と考える。身体中にまとわりついていた汗が吹き飛んで身軽になるように強く。 遠くへ行くんだ。遠くへ行くんだ。遠くへ行くんだ。 昨日、母に抱きすくめられた感覚がふとよみがえる。りん子はふるふると首を振って、窓のふちにゆびをつけた。カタタン、カタタン、カタタン。心地のよい振動が、そのゆびさきから伝わってくる。 カタタン、カタタン、カタタン。 カタタン、カタタン、カタタン……。 ハッと目を覚ますと取りこぼしたビニル袋を男が拾い上げているところだった。 はじめに乗った二両の列車を乗りかえ、次の列車もさらに乗りかえ、いちばん最後に乗った電車はついに一両になった。その玩具のように小さな車体が、ぎぎぎぎぎー、っと高い音低い音両方を上げながら、屋根すらない駅のホームにすべりこむ。 乗ってくる客はひとりもいなかった。代わりに一人の若い男がそこで降りてゆく。車内にはふたりを除いてあと三人しか乗客がいない。全員が、男か女かもわからないような老人ばかりだった。 「次で降りるぞ」 拾ったパンとおにぎりを袋に仕舞い、ふたたび袋をりん子に持たせると男は言った。りん子はうなずく。脇に置いていたリュックサックを背負おうとすると男の大きな腕がそれを制し、持ってやるからと低く呟いた。 前の駅から次の駅までは十分ほどで到着した。見渡して目にはいる風景はもうほとんどどこも同じで、山に田畑に、それからポツポツとまばらに建つ家がすべてだ。方角はおろかみぎひだりさえわからなくなりそうだとりん子はすこし緊張する。 この駅で降りたのはりん子たちの他にもうひとり、ほとんど直角に腰の曲がった老婆がいた。老婆はそのぎこちない身体をゆっくりゆっくりすべらせるように動かし、無人駅のゲートをくぐった。 男もそれにつづく。無人の駅舎は汚れたベンチと止まった時計の他にはなにもない。老婆に倣って握っていた切符を木製の箱に投げいれ、そのしんと静まりかえった場所を抜けた。 表ではカッと照りつける油日が高くのぼっていた。うっと目をすがめると、男は手に提げていたりん子のリュックサックをあさり、中からつばの大きな花柄の帽子を取り出す。母がいれておいてくれたのだろうか。それは見たことのないものだった。 男はりん子の頭にそれをかぶせると、行くぞと短く命令する。深くかぶりすぎて狭くなった視界をちょいちょいと直しりん子は男のあとを歩いた。 駅の周りにあるいくつかの建造物を通りすぎると、そこはもうほとんど平坦でなにもない土地だった。男とりん子はヒビのいったアスファルトの上を太陽に焼かれながら歩き汗を垂らす。男はときおり立ち止まってりん子をふり返りその小さな歩幅が追いつくのを待った。その度にりん子はすこし小走りになって彼の足元まで急ぐ。 それをくり返し十五分ほど歩いてゆくと山の入口のようなところにたどりついた。それはまさに、山の入口、としかいいようがない。木々が左右に避けて道をつくり、アーチのように樹冠を触れ合わせたそれらはしかし道の上に葉を落として堆積させては、その道を暗くうっそりと隠している。 りん子はその道の彼方を見やって、うっと呻いた。先が見えぬほど長くつづく道は当然のごとく山頂をめざしており、つまりは結構な傾斜の上り坂であった。ちらりと男を見上げると男もいい加減うんざりしたような顔でりん子を見る。肩にひっかけていたリュックを持ち直し、顎でしゃくって「この先だ」と言う。 道の傾斜はだいぶん苦しくはあったが、山に入ると日光が遮られてむしろ歩きやすくなった。長く歩く身にとってあの陽光はもはや暴力だ。だからそれさえなければ意外にも足はさくさく動くのだ。 さらに道がいかにも山道らしかったのは初めのうちだけでいくらも行かぬうちにそれは舗装され随分と歩きやすい道になった。降り積もっていた植物も取り除かれて綺麗に整えられたそこは徐々に人の気配が近づいてきている。幅の広い階段に銀色の手すりがあらわれて、そこまでくると目指す先に何があるのかりん子にもだいたい想像がついた。 階段を登りきると、ぐるりと長い山門に囲まれてその巨大な寺はひっそりとそこにあった。チチチチチ、グルッポ、グルッポ、ピロピロピロ。聞いたこともないような山鳥と数種の蝉の声がその静謐を占拠している。山門の前の道は車道らしかったが、アスファルト舗装をいままさに行っている最中で、だからここへは車を寄越すことができなかったのだとりん子は理解した。 男は木でできた古い門をくぐると迷いもなくその中を進んだ。内側には寺務所や堂塔のほかに住居と思われるような真新しい建物もあった。ガラスの窓があり、ごくごく普通のカーテンの模様が外からも見える。 砂利が敷かれ美しく整備されている境内の道をゆき、その最奥にある本堂らしい建築物の前に来ると男はその階段の前で靴を脱いだ。疲れきって呆然としていたりん子にもそうするように言い、その靴を手に持ったまま二人は堂の廊下をぐるりと歩く。勝手知ったる様子で脇の障子戸を遠慮もなく開くと、男はその中に入った。 中は空気がひんやりとしていて心地良い。足裏を癒す畳の感触と荘厳な仏像とに囲まれてりん子はほうっと息を吐いた。 「おお、アクタベか?」 と、そこへ年老いたもの特有のしわがれ声が、語気をはずませてそういった。 「元気そうだな、じーさん」 老人に対して男は大して面白くもなさそうに応える。りん子は思わず男の足元に隠れ、その様子を見守ることにした。 「準備はしておいたぞ。ああ、その子がそうじゃな?」 身を隠したりん子を老人――袈裟を着た住職らしい男が目を細めて見る。張りを失ってやわらかく垂れた頬につるりとした頭、しわしわの目元、ふくよかな身体にそぐわぬやせ細った手足が、彼の老いをあらわしている。 「よう歩いて、疲れたじゃろう」 住職はいたわるように言う。りん子は小さくうなずいた。 「まずは冷たい飲み物を用意してやろう。ほれ、お前さんも来い」 ぎゅうっと皺を深くしてりん子に笑いかけると、それから男に向かって言い、踵を返す。本堂の障子を開けて木の廊下をすすむ。あきらかに一般の参拝者の侵入を許していないその通路を歩いているのは不思議な感じがした。廊下は歩くたびにきゅるるる、と鳥の啼くような音がなる。りん子はぎょっとして足を何度も踏みかえた。その様子を見、住職は声をたてて笑った。 その廊下のつきあたりは先程見た居住空間とひとつづきになっているらしい。途切れた廊下を紡ぐように簀子がしかれ、その先にある扉を開けると中はいかにも普通の民家のようだった。玄関らしいところを上がり客間のような和室で座布団をすすめられる。りん子はわずかに躊躇ったが、無遠慮にどかっと腰を下ろした男の横に、自分もちょこんと座り込んだ。 住職はよく冷えたオレンジジュースをりん子に、麦茶を男に出した。喉がカラカラに渇いていたのでそれは大層美味かった。一息に飲み干すと満足そうにうなずかれる。行儀悪くあぐらをかいた男は、つまらなそうに鼻を鳴らした。 「グシオンは」 「お前さんもせっかちじゃのう。心配せんでもほれ、そこにおる。おおい、グシオン」 ぼそぼそと小声でやりとりをしていたかと思うと、住職は突然何かを呼ぶように声を上げた。そして和室の襖の陰からそれはのそのそとあらわれたのだ。りん子はぎょっとして目を瞠る。 「よ……妖怪!」 たまらず勢いよく立ち上がって、人とも動物とも異なる見たことのない風貌の生き物を指さした。 「何?」 「おお?」 すると二人の男が驚いたようにりん子を見る。黒い男は思いきり顔を歪め、住職は純粋に喫驚という顔をしていた。 「おい……これが見えるのか」 「これ? この、怖い猿のことですか」 見えるんだな、と念を押すように言って、男は苦虫を噛み潰したようにりん子を見下ろす。何のことだかわからずりん子は、男のその、妙に面倒くさそうな、苛立たしげな顔を見返した。 「そうか……お嬢ちゃんには見えるんじゃなあ。なんと皮肉なことじゃ。そうしたら記憶を消すのには、ほんのちょっと、怖い思いをするかもしれんなあ……」 大人ふたりの動揺をりん子は理解しない。どうしてこんなにも意外そうな顔をされているのか、まったくわからなかった。住職の背後で醜い生き物がじっとりん子を見ている。りん子もまたその生き物の、瞳らしい部分をよく見つめた。感情に乏しく動物的ですらないそれ。そういえば彼らは、この異形も含めてどこか似通った気配を持っている。 ――さびしそう。 男も、住職も、猿も。みんなみんなさびしそうだ。 「もう、いい。さっさとしろ」 はあ、とため息をついて男が立ちあがった。りん子も釣られて立ちあがる。 「そう急くな。まったくこれじゃから若いモンはのう」 「もーろくじじい。お前は老い先短いんだからもっと急いだほうがいいぞ」 「なんじゃと」 やれやれ。大儀そうに言って住職も立ちあがる。玄関へ向かい、先ほど来た廊下をふたたび戻って堂に入る。薄暗い堂の中央に住職は座布団を敷いてくれた。男と並んでそこへ座る。先ほどと同じように男は胡座をかき、りん子は正座をしていた。 「お嬢ちゃん。これからちーっと、お嬢ちゃんに魔法をかけるでの。ちょっとのあいだ目をつぶっておいで」 住職はやさしく諭すような声で言う。りん子の正面に正座してぎゅうんと背を丸めるその人の姿はなんだかかわいらしかった。 りん子はとなりの男を見遣った。見上げてくるりん子の瞳に男は一度だけ小さくうなずく。だからりん子も、住職に向かってうなずいた。 「わかりました」 答えると、住職は目元に皺をたたえてにっこり笑い、りん子の頭を撫でた。 りん子は言われたとおりに目を瞑る。途端に線香の匂いが鼻腔をくすぐり、堂の外から聞こえてくる山の音、住職や男の衣擦れの音、それからあの猿の舌なめずりが聞こえてきた。 まなうらに母の姿がよみがえる。泣きわめき、怒り、ほとんど狂ったように笑う母。あのひんやりとした事務所で別れたきりの母。母をなだめすかす父の骨ばったてのひら。 ――もう一度会えるだろうか。 つむった目蓋の奥からひたひたと涙がこみあげてくる。こぼれぬように、もっとぎゅっと目をつむる。 会いたい。 会って話がしたい。 抱きしめてほしい。 泣かないでほしい、笑ってほしい。 あの日まで全部、巻き戻ればいいのに。 そんなふうに考えていると閉じた視界は相変わらず真っ暗だが、ズズっと、たしかに生き物の近づいてくる気配がした。そして。 ……いただきます……。 空気の振動そのもののような、おごそかな声が聞こえる。外の蝉がひときわ大きく鳴いた。  「……ここ、どこ?」 気がつくとりん子は見も知らぬ場所で座り込んでいた。それは寺の本堂のようなところだった。正座をした足がじんじんと痺れだしている。薄暗い堂内はぴったりと障子が閉ざされ、上空から見下ろしてくる巨大な金の仏像がどこか恐ろしくも感じられた。 「おじいさん、だれ?」 りん子はまず、正面に座っている老僧に向かってたずねる。何が起こっているのかまるで分からず多分に混乱していた。 袈裟を着た住職はやさしそうな、でもどこか悲しそうな顔でりん子をのぞきこんだ。それから二三度うなずいて問題はないようじゃなとひとりごとのように言う。 「終わったのか」 突然となりから聞こえてきた低い声にりん子は飛び上がるほど驚いた。首を動かすことができず視線だけでちらりとうかがうと、人相の悪い、おそろしく冷たそうな男がそこにいる。 「ああ、とどこおりなく」 住職は男に向かって応える。これは一体どういうことだと、りん子はほとんど怯えきって視線を泳がせた。 「混乱しておるの。まあ無理もないじゃろう。さて、どう説明したものか……」 「おい、おまえ」 「ひゃっ」 突然声をかけられりん子は肩をすくめて悲鳴をあげる。不快そうに眉をひそめられ、りん子はおずおずと男を見上げた。 「覚えていないな」 「な、何を……」 「……おまえは、道に迷った。ひとりでふらふらと帰り道をさがしているところを、さらに深いところまで迷い込んだ。もうひとりでは帰れない、だから俺が送っていく。いいな、そういうことだ」 「え、え……?」 「お前さん、そりゃ無理があるぞ」 「うるせぇ」 男は強引に、いいな、ともう一度言った。わけもわからずその威圧感にけおされてりん子はうなずく。不機嫌そうな男の声はただ、不思議とおそろしくはなかった。 住職と男に続いてりん子は堂の廊下をゆく。艶のある板廊は歩くたびに鳥の啼くような音がしてりん子は思わず足を止めた。住職はその様子を、ちょっとだけ微笑んでみていた。 りん子は座布団に座ってよく冷えたジュースを飲んでいる。甘酸っぱいオレンジの芳香が口いっぱいに拡がり、かわいた喉にぴっとしみた。カラン、と氷がすべり落ちてきて唇に当たる。その冷たさもまた幸福だった。 「ずいぶん感情的になっておるようじゃの」 「……」 りん子からすこし離れたところで住職と男が言葉を交わしている。住職の膝の上に小さな子どもが手をばたつかせていて、それは先ほど寺の人間らしい作務衣姿の若い男がこの場所に連れてきた子供だ。どうやら住職は男に見せてやるために、まだ小学校にも上がっていなさそうなこの男の子をつれてくるように言ったらしいのだった。 少年、ともまだ呼べないような幼いその子は住職のまとう袈裟のあちこちをいじっては楽しそうに笑う。住職もまたその笑顔を見て顔をほころばせた。 「かわいいじゃろう。ワシの孫の光太郎じゃ。つい先日この子の両親が交通事故で亡くなっての、ワシが引きとってこの寺で育てることになった」 「頭の悪そうな顔をしている。ジジイにそっくりだな」 「ほっほっ」 男はやはり興味もなさそうにそっけなく言った。住職が身体を揺らして笑い、それから光太郎と呼ばれた子供の頬に指先で触れながら、しわしわの顔をもっとしわしわにして、とても静かな声でたずねた。 「アクタベ。何にそれほどいかっておるのじゃ。その娘を憐れんでおるのか」 男はふんっと鼻を鳴らす。りん子はふたりに悟られぬよう、ジュースに夢中であるという振りをしてその会話を聞いていた。 「人は愚かだ」 断定的に男は言う。冷めていて、退屈そうで、うんざりしたような声だ。 「誰も救わないのに説く。けして救われないのに祈る。この娘はどのくらいの間、無駄な懇願を神にしたのかと思うと、なんだかいまいましくてね」 努めて馬鹿にしたような響きに住職は呆れたように首を振った。そしてちらりとりん子を見る。りん子は聞き耳を立てていたのに気づかれたのかと思って、慌ててまたグラスを煽った。 「お嬢さん。よかったら光太郎の相手をしてやってくれんかの? こんな山奥で、この子は遊んでくれる友達もほとんどいないんじゃよ」 住職が突然りん子に近寄ってきて、その幼い少年を差し出した。少年はへらりと人懐こい笑みを浮かべ嬉しそうに声を上げる。りん子はその小さなてのひらをにぎって、こくん、とうなずいた。住職はありがとうと言ってりん子の頭を撫でる。やせた手のひらはこつこつとしていてどことない悲しみをはらんでいた。 「……たしかに、この子は祈ったかもしれん。それだのに救われず絶望したかもしれん。じゃがだからといってその祈りを笑ってやることなど、人であるワシには決して出来んのだ。この先この子が神に祈ることがあるのかどうか、それは分からん。しかしそのとき祈りの中で神は、お前さんの思うものとまったく別のすがたをしているかもしれんのじゃよ」 「どんな姿だろうと神は、神だ。無慈悲で無情で無知で無能な役立たずの存在だ。そんなもの信じたり仰いだりするやつらはどうかしている」 「相変わらず、頑固なやつじゃのう」 住職が笑うと男は、だまれ、と子供のように口を尖らせて低く言った。 「もう思い出すことはないのか」 「それは分からん。この年頃の子どもの記憶はもともとひどく曖昧じゃ。液体のように体の中を流れておる。肉を切り分けるように、綺麗に取り除くことは難しい。この小さな身体に残った記憶の断片を、いつか思い出すことがあるかもしれん。それは明日のことかもしれぬし、十年後のことかもしれぬし、死ぬ間際のことかもしれぬ。だあれにも分からんのじゃよ」 「使えねえ悪魔だな」 「そう言ってやるな。グシオンとて全能の神などではない、お前さんの言うとおり、悪魔なのだから」 「……ああ」 「さあもう行ってやれ。不安そうな顔をしておる。お前がおらねばあの子は家に帰れないんじゃ」 男はすっと立ちあがった。光太郎の頬を撫でたりつねったりしていたりん子の傍らに立ち、じっと見下ろすと、それからやはりあの口調で「帰るぞ」と言った。 住職がりん子から光太郎を受けとり、もう一度ありがとうと頭を撫でてくれた。その表情も手つきもさびしそうでりん子はすこし泣きたくなる。 「おじいさん、さよなら」 「ああ、さようなら」 見送りに出てくれた、背後で手をふる住職の姿をりん子は何度かふり返った。手のひらが右に左に揺れるほど胸のあたりが締めつけられる感じがした。 りん子は男の背を追ってこの家を出る。冷えていた家の中や堂内と違って表は相変わらず茹だるような暑さで、あっという間に汗がにじむ。男は気遣いのない早足でずんずんと歩いていき、りん子はそれについていくのにほとんど駆け足であとを追った。 男の足元に追いつき息を整えながら高いところにある陽を見上げ、それからもう一度寺のほうをふり返ると、しかしふしぎなほどそれは霞んでよく見えなかった。像を歪める熱気のせいなのか、あるいはりん子がもはや、この寺にとって用を果たした存在だからなのか。りん子はぐっと奥歯を噛む。 「さようなら……」 そしてもう二度と、その寺をふり返ることはなかった。  山の道はくだりになっていてけっこうな勢いがつく。歩いていてはじめて気がついたことだがどうやら足がずいぶんと疲れていた。気を抜くとがくがくと震えだすほどだ。いつのまにこんなにも疲労をため込んだのだろうとりん子は不思議に思った。 南天を過ぎた太陽はそれでもじりじりと照りつけ、そこに山のざわめきが加わる。鳥や蝉や木々のふれあう音がどことなくおそろしかった。 寺の山門を出たときから妙な感覚がうまれていた。それは形容しがたい孔のようなイメージで、その孔が身体のどことも分からないどこかに空いているような気がするのだ。しかしその正体をつかむ余裕などないくらい男の足どりにはためらいがない。 待ってください、とりん子は言おうとした。もうすこしゆっくり歩いてほしい。でもこの男がどういうつもりでりん子を導いているのか、それが分からないのだ。待ってと言って、待ってくれる人なのか。そもそもどうしてりん子はこんな森の中を歩いているのか。帰り道というけれど、だって通ったおぼえがないのに? ぐっと言葉を飲みこんでりん子はひたすら足を動かした。木陰が顔に当たってきらきらと明滅する。 とにかくこの森を出なければならないのだと、りん子は思った。何もかも分からないながらに、それだけをたしかに、ハッキリと思った。 そしてこの森を出るためには目の前をゆく黒いスーツをきた男の道引が必要だった。ほかに頼れるものがなにもないのだ。それに、どうしてかこの男をうたがわなくてもよいとりん子は確信していた。 階段が坂になり坂が山道になる。緑もだんだんと深くなり、比例して不安も大きくなった。見上げると林冠の隙間に鳥がよぎり、ぎゃあ、と一声鳴く。 「あっ」 上空に気を取られていたせいで、足元に隆起した木根にひっかかって転びそうになる。すんでのところで反対の足を前に出し転倒はまぬかれたが、その拍子にピシッとヒビの入るような痛みが足首から走った。 男はそこではじめて、ようやく足を止めた。ふりかえってうずくまるりん子を見、チッと舌打ちをしたかと思うとざくざくと植物を踏み鳴らしながら近寄ってきた。 「挫いたか」 男の影が太陽を遮ってりん子に覆いかぶさる。痛いほどに肌を焼いていた熱線が絶えてりん子はほっとした。 「だいじょうぶ、です」 足首にふれようとする男の大きな手のひらを制してりん子は主張する。立ち止まってはいけないのだと思っていたから。歩きつづけなければ、そして一刻もはやくこの森を抜けなければならないのだと。これくらいの痛みなら我慢できる。だから先を急ぐべきだと、そう思った。 焦燥の色を浮かべるりん子の表情をしばらく睨んでから、男はあきらめたようにため息をつく。そして手をさしのべてりん子を立たせてくれた。 「もう少しだ」 りん子はうなずいた。男はまたりん子の前を歩きはじめる。その歩調がたしかにゆるんでいた。りん子は唇をひきむすんでひたすら歩く。 もう少しだ。もう少しで、森を抜けることができる。このわけのわからない森を。空洞の森を。つかのまの異次元を。 蝉の声が背を押すように絶えず鳴りつづけた。りん子は前へ前へ進んでゆく。男の背を追いかける。歩みを止めれば泣き出してしまいそうだった。 帰るんだ。でも、どこへ? 帰り道というものは、往く道がなければ決してうまれない。おぼえていないのだ。ほんとうに。世界に――もっと別の何かに――ほろりと手放されてしまったように、見捨てられてしまったように、りん子は足元が覚束ない。 「オイ」 「ひゃっ」 前を行っていた黒い影がとつぜんふり返った。りん子は不躾なほど飛び上がっておどろき、どうやら男の不興を買ったらしい。男はいらついた顔をして大股で近づいてくる。ふたたび太陽が遮られて、叩かれる、とりん子が身をすくめると。 「わっ」 ふわりと身体が宙を舞った。 抱き上げられたのだ、と気がつくまでにしばらくかかった。 男の目線が近くにある。そうしてりん子を覗きこんでいた。それはやはり黒くて穏やかではないのに、決しておそろしくはない。その瞳にのぞきこまれるとりん子はどうしてかひたすらに、寂しく、なるのだった。 「足が痛いんだろう。ならそう言え」 男が呆れたように言う。りん子を片手にかかえたまま、持ちあげられた時に落とした帽子を拾ってかぶせてくれる。 ジジジジジッ、と蝉の飛び立った音がした。森の中は相変わらずざわついており木々の影がせわしなく動いている。汗ばんだ身体をいといもせずに抱き上げた腕から熱い体温が伝わってきて、ただひとつ、それだけがりん子にはおそろしかった。 「…………どうした」 気づけば、頬に大粒のしずくがつたっている。ぼろぼろとこぼれてしまった涙をやはり苛立たしげに男は拭った。瞼を圧迫するように乱暴に手の甲で拭われてりん子は視界をふさがれる。だからりん子はその手の甲に顔面を押しつけるようにして、それから大声で思いきり、泣くことにした。 うあぁぁん、うえええ、ふぇぇ、ひっ、く。 周囲から降ってくる蝉の声にも負けないくらい大きな声だったと思う。遠慮もためらいもなく、それは森中にわんわんと響いた。木々がざわめくのをやめ、戸惑ったように沈黙を守っている。男もまた無言だった。 りん子は男のてのひらを両手でぎゅうっと握りしめすがりつくように顔を押しつけた。何が悲しいのか、それはりん子自身にもよく分からなかった。けれどあとからあとから溢れでてくるものを止める方法が分からない。大声を上げなければいけないような気すらした。 男は黙っていた。りん子は泣き喚いた。そしてふっと握っていたてのひらに拒絶をされたかと思うと、次のしゅんかん男の肩口に瞼を押しつけられていた。先ほどまで涙を受け止めていたてのひらはりん子の頭を包みこみ、乱暴にわしゃわしゃと髪をかき回す。りん子を抱えていた腕が重い荷物を持っているときにそうするように一度大きく揺らされて、りん子の身体はひゅんっと浮く。されるがままにして、それでもりん子は泣くのをやめなかった。 男は泣きつづけるりん子を抱えたまま森の道を下りはじめた。その足が前に後ろに動くたび、腕の中のりん子の身体もゆさゆさと揺れる。薄い布地のワンピースはすっかり汗ばんでいて靴下も泥まみれ。それらの汚れが男のスーツにすこしずつ移っていったが、男は気にせずにりん子を抱え歩いた。 目を眇めたくなるほどにまばゆい光がひらけはじめた頭上から燦々と降りかかってくる。けれどりん子に見えていたのは黒い肩と、その隙間からのぞく、男のたしかな足取りだけだ。いつの間にか声も涙も枯れはてていた。 ――森を抜ける……。 この人の腕の中で。りん子はまなうらに残った涙を二三粒こぼしながら、そのやさしい、おだやかな揺らぎ方を知覚した。そうしてそれを、おぼえておけるだろうかと、ただしずかに考えた。 おぼえておきたい。ずっとずっと、どこまでも。うんとうんと、遠くまで。 この舟の上に、いたい。  瞳の表面にゆらゆらと浮かんだ涙を、芥辺は目を細めて見ていた。水面に映る歪んだ像を、その自己を、祈りのように見つめつづけていた。 「……」 あの日、夢の話をした。 そこに見たことのないものは出てこないという。それは光太郎が言った言葉だ。 人間は自分自身が思うほど無秩序な回路を持ちはしない。そのつくりは精巧で作為的で、あらゆる機能が綿密につながりあい相互に作用している。そういうふうにできているのだ。 あの事務所のソファでどんな夢を見るのかと聞いてきた芥辺のむずかしそうな顔に、りん子はたしかに何かの予感をおぼえた。何かが始まりそうな、あるいは何かが終わってしまいそうな、そういう予感だ。 このままでいたいと思うほど今の日常に満ち足りていたわけでもない。しかし変化を望むほど、欠けたものがあったわけでもなかった。だからその予感はどこか不穏でおそろしくて。 そんな折に彼女たちがあらわれたことは、一体だれの意図だったのだろう。鳴りつづけた警鐘に聞こえないふりをしたのも、普段なら気にかけぬ瑣末な痼を見逃さなかったのも、誰かを救いたいと、思ったことも。だれの、どんな、意図だったのだろう。 分からない、けれど。 「アクタベさんだったんですね」 ふるえる声でりん子は言う。 「私、ずうっと、思い出すことができなくて」 視線を彷徨わせながら喉からしぼり出すように口にする。ふいに彼の背後の空が明るくなった。雲が晴れ、その隙間から生まれたてのようにやわらかな陽の光があらわれはじめる。 「それが君の母親の望みだった」 芥辺はようやく、端的にそれだけを告げた。わかっているというようにりん子はうなずく。 「でも、私の望みではありませんでした」 そう言うと、芥辺の表情がふっと翳った。それからほんのわずか切なさを帯びる。ああ言い方を間違えたかもしれないとりん子は不安になって、慌てて言葉を加える。 「私ね、嬉しいんです」 「嬉しい?」 「全部、思い出すことができて。忘れてたこと、アクタベさんが、助けてくれたこと」 「……」 本当に嬉しかった。あの森のこと、我慢できずに泣いてしまったこと、それでも拒まれず、慰めてもらえたこと。それから森を、抜け出せたこと。それを思い出せて、嬉しかった。 「アクタベさん。本当に、ほんとうに……」 そうして、りん子が言葉を紡ぎきる前に。 大きな影は質量をもってようやくりん子に触れた。 りん子を見下ろしていた瞳がもう、埋められて見えなくなった。ずっしりと覆いかぶさったその重みは硬く骨ばって、分厚くて、それからとてもあたたかかった。 肩口に押し付けられた彼の口元から深くて静かな呼吸がくり返される。規則的に、それは記憶を優しくなでつけるようにりん子の首すじをくすぐったくさせた。あのときと逆だ。そう思う。 りん子はそろそろと手のひらを持ち上げて彼の背中にかるく触れた。それから嗚呼と嘆息する。ようやくだ、と。ようやく見つけたと。肩甲骨のとびだしたそこに、人の骨格に、だって涙が出るほどずっと、ずっと触れたかったのだ。 ぼろぼろと雫が溢れてとまらない。それもまたあのときと同じだ。横たわったりん子のまなじりから、それは米噛をつたってシーツにしみた。 ――神様なんていない。 けれどりん子はあの森を抜けたのだ。それをたしかに、覚えているから。 (続く) |