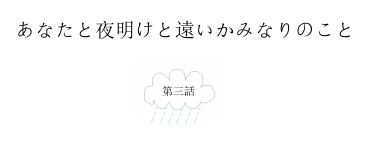 この日は朝から、雨が降っていた。 昨夜遅くにとうとう降りだした雨はやがて烈しさを増し、それは絶え間なく重たく、街をあまねく灰色に沈めていた。よどんだ空気に遠くの建造物の稜線がおおい隠され、低く唸るような雨音は獰猛なけものの眠りのようでもあった。 息苦しい高湿の大気。停滞する濁った雲。人々がかざす暗い色の傘。 それらすべてが、まるでこの街のどこかで眠りつづける怪物を目覚めさせまいとする意思のようにつながり合って充満している。隅々まで拡がった静寂がだから、むしろ恐ろしく感じられた。これは、そういう雨の日のことだった。 「どう。見える?」 「ううーん……」 りん子が声をかけても、鞠枝は唇をうすくひらいた恰好のままちょっとうなっただけだった。手にした双眼鏡の角度を何度か試すように変えてみているが、どうやらあまり功を奏した気配はない。雨だれがぱたぱたと鞠枝の白い指先にいくつもぶつかってはじける。形のきれいな爪にのったしずくは美しいマニキュアのようにひかった。 「なんというか、雨と霧でほとんど何も」 「やっぱりだめかあ」 覗きこんでいた双眼鏡から目を離し鞠枝は疲れたように言う。鞠枝の手からその双眼鏡をうけとり同じようにレンズを覗いてみたが、なるほど鞠枝の言うとおり見えたのは煤けたような灰色の景色だけで、四角い建物は空との境界線すら曖昧だった。 「それにしても、この状況はちょっと怪しすぎませんか」 「うっ」 顔を上げて辺りを見まわし鞠枝は冷静に言った。双眼鏡を下ろして同じように視線をめぐらし、たしかにこれは相当だと思った。 雨のやまない公園には人の姿はまるでない。公園とはいっても、そもそも遊具の類がひとつもなく、木製のベンチといくつかの木が植えられているだけの簡素な休憩所のような場所だ。晴れの日には昼休みの会社員や犬の散歩をする人が訪れることはあるようだが、この雨ではそれもなかった。そんな閑散とした場所で女が二人、双眼鏡片手に高層マンションを見上げている様子は一歩間違えれば通報されてもおかしくないほどには不審である。 「でも他に手がかりはないし」 「そうなんですよね」 鞠枝は小さなため息をついて正面にそびえる巨大なマンションをふたたび仰いだ。幾何文様のように同じデザインの部屋が無数に並んでいるそれはしかしつれなく、まるで廃墟のようにその内情は杳として知れなかった。 グリーンズマンション802。その数字を何度も唱えながら、いち、に、とフロアを数え上げているうちに果たしてたどりついたそこが本当に八階であるのかわからなくなった。森の中の一本の木のようにその一室は巧妙に隠されているのだ。雨のせいで布団や衣類がほとんど干されていないこともまた、部屋々々の差別化を困難にした。 そもそも何故、鞠枝とりん子がこんな不審者まがいのことをしているのかと言えば、話は一時間前にさかのぼる。 「本当、だったんだ……」 テーブルにばら蒔かれた何枚もの写真を覗きこんでもりん子は碌な言葉を思いつかずに、呆けた声でそれだけを言った。嫌悪や軽蔑などはいっそ湧かず、ただただ本当だったんだと、事実に対するわずかな驚愕があるのみであとはほとんど何の感慨もなかった。大した興味もなさそうに傍らに立っていた芥辺は無言のままかがみ、乱雑に散らかった写真を一枚残らずかき集めると手に持っていた封筒に仕舞う。 「そういうことだから」 「は、はい」 何が『そういうこと』なのかはよく分からないがりん子は咄嗟に肯いていた。釣られるように芥辺の手元に収まる茶色い封筒を見つめたがやはりこれといった感想が浮かんでくるわけでもない。ほうっとしたりん子の様子をしばらく見ていた芥辺は小さく舌打ちをして(何故!)、それから踵を返すと『多分そんなに掛からないから』と平坦に言い、りん子に留守を任せて出ていった。 芥辺の傍らにはまだ本調子ではないながら一応回復したらしいベルゼブブの姿があった。なるほど病み上がりのやつれた顔をして三キロは痩せましたよと言っていた。悪魔に人間の単位系が浸透していたことには驚きである。とにかくふたりは、だからおそらくは三崎の勤務先に向かったのだろう。もはや言い逃れは出来ない。暗闇に溶けるような”あの姿”を思い出し、すっと背筋が寒くなった。 彼は職場の人間が大勢いる前で、あの写真を衒われるのかもしれない。そしてベルゼブブの見えざる力によって強制的に自供をさせられ、くずおれるようにすべてを失うのかもしれない。 その陰惨な光景を想像しながら、それでもりん子はものを思うことなく細い息を吐いた。夜の道で、暗い陰で、家の前で、底知れぬ空洞のような目をして何かを一心に見つめる男の姿に、救いなど与えてはやれない。一昨夜りん子の正面で機嫌よく言葉を話していたあの男はやはり、幼気な一少女に執着する異常な人間だったのだ。要するにまた、そういう人間のひとりに出遭ってしまったというだけの話だ。 閉ざされた事務所のドアをりん子は見遣った。扉は沈黙し、物言うことなどありはしない。 結局。彼に感じた既視感の正体を知ることは叶わなかった。 りん子はほとんど垂直に落ちていく窓の外の雨滴を見やる。それは時の経過とともに徐々に強まっているようだった。のがれようもなく身体を濡らす雨は執拗に執拗にそこにとどまろうとしている。とらえて、はなさず、すべてを水中に沈めようとしているのだ。 はたして本当に彼を見たことなどあったのだろうか。りん子は三崎の仕草やかおかたちや言葉じりを思い出そうとするが、うまくいかなかった。パソコンのデータベースに残っている三崎の情報をよびだして、ああそうだこの人、とようやく思うことができるくらいなのだ。それほど曖昧にしか記憶出来ていない人間を、どうして『知っている』などと思うのだろうか。その意味や理由を、知りたいと思わないでもない。 でも仕方がない。逸した機会は二度とはめぐってこない。これから数日もすればこのわだかまりのようなものもすっかり日常にまぎれてしまうだろう。それでいい。それが正しいのだ。 りん子は開いたファイルのウィンドウを閉じた。それはパッと消えて、味気のないデスクトップ画面があらわれる。ついで熱を放つパソコンの電源を落とした。 そこへ、一本の電話が入った。 「はい、芥辺探偵事務所です」 『あっ……さ、佐隈さん?』 「あれ。もしかして、鞠枝ちゃん?」 電話口で不安気にりん子の名を呼んだのは、あの鞠枝だった。鞠枝の声は焦り、動揺し、冷静さを欠いたどもりかたで何度か言葉をつまらせた。受話器の向こうではサアアアアアと掠れたようなノイズが聞こえている。それはどうやら雨の音であるらしい。鞠枝はその電話を外から掛けてきているようだった。 『千春ちゃんが、いないんです』 「いない?」 『電話が通じないんです。メールも返ってこないし、家に行ったら昨日から帰ってないらしくて。ご両親も心配されてさっき警察に届けるって。私、他に頼れる人が思いつかなくて、それで』 どうしよう、と鞠枝は消えそうな声で言った。それはもはやりん子に訴えているのではなく、ただどうしようと途方にくれて口から漏れた言葉であるらしかった。 「鞠枝ちゃん、落ち着いて。千春ちゃんと最後にあったのはいつ?」 『昨日の夕方です。新宿の本屋に行くのに付き合ってもらって、駅で別れました』 「それからパッタリ連絡がとれないの」 『そうなんです。夜にメールしても返ってこなくて。その時はもう寝ちゃってるのかなって思ってあまり気にしてなかったんですけど、今朝になってもメールはないし、それに学校へいくときいつも待ち合わせしている場所に来なかったんです。千春ちゃんって時間には厳しくて、一回も遅れたことがないから何かあったのかと思って電話したら、でもやっぱり出なく、て』 「千春ちゃんの行き先に心当たりは?」 『それが、ぜんぜん、わからないんです……私、』 どうしよう、と鞠枝はもう一度言った。切迫していまにも泣き出しそうな声だ。りん子は慌てて言葉を添える。 「鞠枝ちゃんはいまどこにいるの?」 『新宿です。昨日千春ちゃんと別れたのが東南口だったので、そこに』 「わかった。申し訳ないんだけどアクタベさんは今出てるの。例の三崎さんのところだと思うんだけど、とりあえず私が行くし、多分二十分くらいで着くから、鞠枝ちゃんはそこを動かないで。一応私の携帯番号教えとくね。いい?」 ちょっとまってください、と鞠枝が言って何かを取り出す音をたてるのを待ってから、りん子は自分の携帯番号を諳んじる。 『はい……はい……、わかりました。すみません、本当に』 鞠枝の消え入りそうな声が何度も謝罪を繰り返した。りん子は大丈夫と気にしないでをその度に言い、受話器をいささか乱暴に置くと鞄を持って事務所を出た。 事務所を出る前、りん子は一瞬だけ足を止めてがらんとしてしまう室内をふりかえった。空調を止めてしまうと室内にはすぐに雨の気配がみちる。 何か書置きをしていったほうがいいだろうか。ふと考えたが、いい文句が浮かばなかった。ちょっと出てきます、などというのは上司に対する書置きにはふさわしくないように思われた。それから腕時計をみて、そうして考えている時間が勿体無く感じ、ふたたび踵を返して事務所のドアに鍵を掛ける。多分大丈夫だろう。芥辺はりん子の携帯番号を知っているし、何かあれば掛けてくるはずだ。頃合いをみて、りん子が事務所に電話をかけてもいい。そう思ってドアを離れる。 ビルの階段のコンクリートも心持ち膨張して、生ぬるい空気がその辺りを漂っていた。 巨大な駅の入り口の前で鞠枝は亡霊のような顔色をして立っていた。桃色の傘に強く雨があたり、はじけてぼうっと白い膜をつくっている。りん子が駆けよって声をかけても、上げられたおもてはやはり青白く精彩を欠いていた。 肩や足元が濡れ、それは鞠枝に似合わぬ汚れを靴とセーラー服に附ける。しかしそれでいて、さくまさん、とりん子を呼んだ少女の声は意外にもハッキリと、力強かった。 鞠枝を連れてひとまず近くの喫茶店に入る。店内は雨にも関わらず混み合っていて人の話し声がうるさかった。鞠枝は抹茶のドリンクを、りん子はコーヒーをひとつ頼み窓際の席を見つけて座る。濡れた身体は室内の涼しい風に必要以上に冷えた。 「いきなりよびだしたりして、本当にすみません」 鞠枝はまずいちばんにそう詫びた。生クリームのたっぷりのったドリンクにストローをつきさし、くわえる。 「いいって。どうせやることもなくて暇だったから」 そういったりん子を見上げる鞠枝の頬はわずかに赤みを取り戻していた。りん子はそれをたしかめてから、それで、と話を切り出した。 「千春ちゃんがいなくなったっていうのは、確かなの」 「高校の友人のところへは行っていないそうです。もっとも千春ちゃんの部活の友達のことはよく知らないので、そのほうは確かめてないんですが。いずれにしても電話もメールも通じないっていうのはやっぱりおかしいと思います」 「そうだね。彼女の性格上、無断で外泊っていうのも考えにくそうだし。やっぱり何かあったのかも」 「何か」 「ああ、ごめん、縁起でもないこと……」 鞠枝はふるふると首を振った。わたしもそうおもいます、と弱々しく同意して、小さな口でまたストローをくわえた。 実を言うとこのあいだ、りん子はあるひとつの可能性をずっと考えていた。積極的にそれを切り出すことはおおいにためらわれたが、いま考えつくかぎりでもっとも有り得そうな推測である。言うか、言うまいか。 鞠枝は落ち着かなくストローを噛む。歯のあとがいくつもいくつもついて、それはこの可憐な少女にはあまり似合わない。 「これは、あくまで推測に過ぎないんですけど」 鞠枝がためらいがちに口火を切るので、りん子もまた少し緊張してふりかえる。 「なあに」 「根拠はないんです。ないんですけど……たとえば千春ちゃんがいなくなったことに、三崎先生が関わっている可能性って、あると思いますか」 少女は、りん子の考えを見透かしたように言った。 窓の外でざあっと水を跳ねさせながら一台の車が通りすぎる。その車がすっかり見えなくなるのを待ち、周囲をうかがってから鞠枝は思いつめた目でりん子を見た。 「……三崎さんが千春ちゃんに何かしたってこと?」 してはいけない話をするようにりん子も声をひそめて応える。 「わかりません。でもこのタイミングでしょう。無関係っていうほうが意外な気がしませんか」 「それはそうだけど……」 鞠絵の言葉は前置きのわりにずいぶんと確信的だった。そこにはこの年代の少女特有の、悪と思い込んだものを最後まで悪と決めつけておきたい、あの一途さがある。鞠枝の中でいま三崎浩一は純然たる悪なのだ。病的な瞳で鞠枝を覗き、千春を動かし、二人を巻き込んだいとわしき悪なのだ。 だが、単なる勘らしいそれも、あながち侮れたものではないとりん子は思う。少なくとも三崎は鞠枝のストーカーであったわけだし、それを隠して平然と振る舞っていられる異常さを持っている。平凡そうな外貌のうちには粘度の高い執着心がうごめいているのだ。三崎と千春が何らかの接触をしたとして、その結果がいまの千春の不在だと考えることは決して無理のある論理ではなかった。 ただ、鞠枝の――それはほとんどりん子自身のものと違わなかったが――その推理を支持するにはどうしても気になることがある。りん子は芥辺の、あの低い声を思い出していたのだ。 「行ってみる?」 「え?」 「三崎さんのマンション。私、住所なら分かるよ」 鞠枝はさっと顔を曇らせる。 「でも……いいんですか?」 「そうしたくて、私を呼んだんじゃないの?」 「……」 「本当はね。私も、関わるなって言われてるんだ。このあいだ偶然三崎さんに会ったんだけど、そのこと話したら思いっきり怒られて」 「それじゃ、」 「それでも、確かめたい? 可能性があるなら行ってみたい?」 選択を鞠枝に委ねるのはすこしずるい気もした。責任のがれめいていくらか後ろめたくもある。しかし鞠枝が望まない限り、りん子はそれをするつもりはないのだ。 どうする、とたずねた自分の声にどこか責めるような色がにじんでいたことにりん子は驚いた。芥辺の言いつけを破り、さらにこの少女を危険に晒すことに少なからず抵抗があるのかもしれない。 「行きたいです。確かめたい、どうしても……千春ちゃんを見つけたい」 けれど鞠枝は先がつぶれるほど噛んだストローに視線を注ぎながら、ハッキリと言った。りん子はうなずいて、 「じゃあ行こう」 と、それは予想していた通りの言葉に、応える。 そして、ふたりは三崎浩一の住むマンションへやってきたのだが、まさかいきなり正面から訪ねてゆくわけにもいかず、とりあえず外からそのベランダをうかがってみようということになった。そうして、この不審行動だったわけである。どうかするとストーカーはこちらのほうだと思わなくもなかったが洒落にならないので口にするのはやめた。 「でもすごいよね、ふたりとも。お互いがほんっとうに大事なんだ。私親友とかっていたことないから、そういうのすこし憧れちゃうなあ」 濡れた手や髪をタオルでぬぐいながらりん子はやはり不安そうにしている鞠枝に言った。 雨が激しくなってきたので一時的に雨宿りをすることにして、ふたりはルーフのあるベンチに腰掛けている。しかし鞠枝は座っているのが落ち着かないらしくルーフを支える柱の一本に指をついて雨の向こうをじっと見ていた。雨の向こうには霧がある。霧の向こうに、鞠枝の見たいものはあるのだろうか。 「幼稚園からずっと一緒だったんです。でも長く一緒に居すぎて、もう仲が良いとか悪いとか、そういう感じじゃないんですよ」 「だけどこうして雨の中必死になってるって、それだけですごいことだとおもうけどなあ」 りん子が言っても、鞠枝はうつむいて応えはしなかった。 りん子はなんとなく中学や高校の友人たちの面々を思い出してみた。どの顔もひとしくなつかしかったし、しかしどの顔もひとしくうすれていた。地元を離れた今では彼らとはほとんど会うこともない。だからそれはりん子だけが一方的に薄情なのではなくて、おそらくは彼らのほうも同じようにりん子を忘れているだろうと思うのだ。自分はそういうつきあい方しかしてこなかったし、たぶんこれからもそうだろう。たとえばりん子が何らかの事由で姿をくらませたとしても、こんなふうに必死になってくれる人はいない。いないだろうなあ、と淡白に考える。自嘲の心すらそこには生まれなかった。 「……千春ちゃんは、」 黙って雨を見ていた鞠枝がやはり視線は動かさないまま独白のように、どこか懐かしむような顔をして口を開いた。 「千春ちゃんは、人と自分との境界線をうまく引けないんです。他人のことも自分の問題だと思ってしまう。昔からそういうところがありました。さっき佐隈さん、わたしたちをお互いが大事、と言いましたね。でもやっぱり、それは違うと思います。千春ちゃんはわたしを自分の一部みたいに思っている。でもわたしは」 ふぅ、と小さく息をついて、鞠枝はルーフの外へその白い腕を伸ばした。雨だれが音楽のように当たる。その神聖さから、りん子は目を離せない。 「千春ちゃんがわたしのために色んなもの失う気がして、わたしそれが怖いんです」 「怖い?」 鞠枝は一瞬だけりん子の視線をつかまえ、それから小さく笑う。 「千春ちゃんが持って生まれたもの、これから手に入れていくであろうもの、そのすべてがわたしは好きなんです。……ただ、好きなんですよ」 天に向けたてのひらを鞠枝はぎゅうっと握った。雨粒をつかむように、あるいは拒むように。 りん子はわずかに身構えたが、しかし鞠枝の瞳から涙がこぼれることはなかった。彼女はただひたすらに雨の向こうを見つめつづける。本当は何を見ているのか。無論、りん子にはわからない。 「鞠枝ちゃん、肩、濡れちゃってるよ」 「……そうですね、すごく、冷たい」 雨は彼女の皮膚に吸いこまれるように白い腕を叩いた。鞠枝はあのとき――初めて事務所へやってきた日、暑い路上で千春を見送った、あのときと同じ横顔をしている。 サアアアア、とノイズめいた雨音が耳に煩わしく響いた。何かが目覚める予感がする。でも、何がだろう。何が眠っているというのだろう。雨の中で、ジジジッと一匹の蝉が飛び立った。 「行こうか」 「え?」 ほとんど耐えかねて、りん子はそれを口にしていた。 「ここからじゃ何も見えない。何も変わらないよ。本当はあんまり危険なことはすすめたくないんだけど、」 りん子は一呼吸おく。芥辺にはひどく叱られるだろう。しかしここまで来ておいて、遠目にマンションを見上げたというだけではあまりに情けない。 なにより事態は一刻を争う。どういう事情で千春がいなくなったにせよ、発見が遅れれば何が起こるか分からない。そうだ、そういえば千春が依頼にやってきた時もこう言ったではないか。 何かあってからでは遅いのだと。 まさにその通りだ。乗りかかった船という言葉もある。すっと息を吸ってりん子は言い放った。 「やれるだけのこと、やろう」 鞠枝の瞳がはじめて潤む。そして頷き、もういちど雨の向こうを見た。  「あ、もしかしてここ」 「オートロックですね」 「あちゃあ」 りん子は大げさな動作で額に手を当てる。ようやく決意してやって来たのに敵の牙城たるこのマンションはどうあってもふたりを侵入させるつもりはないらしい。ガラス一枚を隔てた向こうには隅々までよく磨かれた清潔な廊下が続いている。死角になって見えはしないがごく手前のあたりにエレベーターがあるようだ。あのガラスドアさえ通りすぎれば千春に手が届くかもしれないというのに。 不審にならない程度の距離をおいてマンションの入口へ近づき、頑然と閉ざされたその扉を見る。ほとんど人の気配はなかった。裕福な一人住まいの多いらしいこのマンションの住人が、平日のこんな時間に出てくることはなかなか望みも薄そうだ。 どうしたものかと口元に手を当てて考えていると、鞠枝がふと思いついたように言った。 「あの、ちょっと考えたんですけど」 「うん?」 「見えますか、あそこ。防犯カメラがありますよね」 鞠枝がすっと伸ばした指の線先をたどると、たしかにそれらしいものが見える。もっとも視力の低いりん子には雨壁に隔たれたそれはカメラであると言われればそうとも見えるという程度にしか認識できない。しかし鞠枝の澄んだ黒瞳には明瞭なひらめきそのもののように見えているようであった。 「たとえばですよ。本当に三崎先生が千春ちゃんを何らかの理由で拉致……というか、このマンションへ連れてきたとして、そんな目立つ行動を取れたでしょうか。いつ、誰に見られるともしれない状況で? 仮に誰の目にも止まらなかったとしたって、映像を見られたら一発でおしまいですよ」 どうも、鞠枝のほうが探偵らしい風情である。りん子はふむ、と考えて鞠枝の言わんとしていることを察した。 「たしかに。千春ちゃんが自分の意志で三崎先生の家に上がるとは考えにくいし、むりやり連れてこられたのなら抵抗するはず。もし抵抗ができないような状況だったとしても、いずれにせよその二人連れは悪目立ちするね。住人に見られたりしたら変な噂になりかねない」 鞠枝は深くうなずいた。 「そう。だから千春ちゃんを部屋に連れていくのはむずかしいと思うんです。もっと別の……誰にも見られず、かつ逃げられる心配のないところ、たとえば」 「車の中、とか?」 アッと目を見開いて鞠枝はもう一度うなずいた。 「地下に駐車場があるみたいだった。たしかあそこなら外からも入れたはず。よし、行ってみよう」 「はい!」 地下駐車場へは思いのほか簡単に入ることができた。うすぐらいコンクリートの壁、床、天井。そのどれもにうっそりと埃がつもっている。天井から漏れ出しているらしい雨が壁を伝っていて、濡れたその部分だけがやわらかそうに膨らんでいた。表とちがって変に寒い。そしてここにもやはり、人の気配はなかった。 「……三崎さんの車、どんなのか知ってる」 「……あの頃から変わっていないのであれば、たしかネイビーの……」 ふたりはその広大なダンジョンのほんの入口あたりで立ち尽くす。予想のできたことではあるが駐車場には無数の車がならんでいて、そのどれもが代わり映えのしないありふれた乗用車ばかりである。この中から目的のただ一台を捜しだすことはいくらか骨の折れる作業になるだろう。 りん子はため息をついた。事あるごとに往く手を阻まれている気がする。それは己の向こう見ずな行動のせいでも確かにあるが、しかしどこかに誰かの意思が噛んでいるのではないかと疑わずにはいられなかった。 白い蛍光灯のあかりが寒々しく地下を照らしている。宛てもなく歩きはじめると靴音が洞窟の中の水音のように波打って拡がった。打ちっぱなしのコンクリート壁を背に延々と続く車の列。それらを区画する白い線をたどりながら奥の方へすすむ。 「A−5、A−6、A−7……」 歩きながらりん子は時折あらわれる柱に大きく書かれたブロック名を読み上げる。 「A−8、A−9、A−10、B−1、B−2……」 AブロックからBブロックへ移るとそのペイントは黄色から黄緑へと変化した。 どうやらアルファベットはAからDの四種類。各文字ごとに10までナンバリングされ、さらに一ブロックには八台の車が収容できるらしいとわかった。つまり単純計算で、三百二十台分の駐車スペースがあることになる。この中からナンバーはおろか車種すら不明のただ一台を捜しだすことはやはり容易ではないだろう。ちらりと鞠枝を見やると、きゅっとくちびるを引き結んでむずかしい顔をしている。 最奥のD−10ブロックまでたどりつくと地上へつながるエレベーターがあり、その横に駐車場の内部案内図が貼り出されていた。りん子と鞠枝はその前に立ち、案内図を覗きこむ。 「やっぱり間違いないみたいだね。三百二十台か……」 ふたりはその前でううんと唸る。ここまで来たはいいが肝心の車が見つけられないのではどうしようもない。 案内図は柱に書かれていたブロックの位置をわかりやすく記していて、その色分けも先ほど見たペイントに対応している。Aは黄色、Bは黄緑、Cは水色、Dは桃色。10ブロックまで。八台収容。 「あ、ちょっとまって。いけるかも」 「え?」 案内図を凝視したまま、はっと閃いてりん子は言った。 「このマンション、確か同じつくりの建物が四棟あったよね。それで、各棟の階数は十。各フロアの部屋数は八、じゃ、なかった……?」 「あ!」 「そう、つまりAからDっていうアルファベットは何号棟かを、ブロックの数字は階数を、それで各部屋の番号が、この……」 「ラインの横に書かれている数字ってことですね?」 鞠枝は目をかがやかせて足元にある数字を指さした。 りん子はうなずく。 「となると、確か三崎さんの部屋は第三号棟の802号室だからC−8ブロック、二番目のスペースに停まってるはずだ」 ふたりは勢いよく案内図をふりかえり、じぃっと睨む。ここからDブロックを通り過ぎ、その向こうの水色で記されたエリアの左から三番目のブロック。今通ってきた道だからおおよその見当はついている。大体の位置を把握するとほとんど駆け出すようにそこへ向かった。 言葉はない。胸が高鳴っているのは急な運動のためか、千春を見つけられるかもしれないという興奮のためか。りん子と鞠枝は、それぞれがそれぞれ異なった意味で身体をふるわせていた。 りん子は駆けながらあの森のことを思い出していた。どうもこの件に関わるようになってから、妙なフラッシュバックが多い。そしてその頻度や濃度は徐々に高まっているような気がした。喉に刺さった骨がとれかかっている。あと少しで、何かを思い出せそうな気がするのだ。 そしてふと不安にかられる。 思い出してもよいのだろうか、本当に? 忘却という機構は、すなわち防御反応だ。忘れていることにはそれなりの意味がある。そうであることが、得てして多いものだ。 心臓が烈しく脈打った。息の根をとめてしまいそうになるくらいの烈しさだった。 それでも脚は動く。鞠枝もまた駆けるのをやめない。桃色のペイントを抜けて、柱に書かれた文字が水色に変わった。C−10、C−9…… 「C−8!!」 似合わぬ大声を鞠枝はあげた。視線を足元へとうつしてたどり、向こうから二番目のスペースを青ざめた目で睨んだ。 「ありました! ネイビーの……間違いありません。三崎先生の車です」 途端歩調をゆるめて、一歩一歩、ゆっくりと振り下ろされる刃のように冷たく、鞠枝はその車へと近寄った。 ネイビーブルーのそれは指紋も傷もないきれいな車体をしていた。外国車の高級ブランドともなれば話は別だが、りん子は車のことにはそれほど詳しくない。だからこの車がどのくらいの値のするものなのかはわからない。が、しかし一目見て、持ち主はこの車を相当大事にしているらしいということは想像がつく。なにしろ鞠枝が知っているくらい昔からこの車に乗っているというのだ。反して、この、かがやき。 鞠枝は緊張した面持ちで外のウィンドウから運転席や助手席をのぞきこむ。 遮光フィルムのせいでハッキリとは見えないが黒いシートは何の変哲もない、それどころか潔癖なほどになにもない様子だった。じっと目を凝らしてもそこには新車同然のビニル臭そうな黒があるだけである。 足音を忍ばせて移動し、後部座席ものぞきこむ。しかしやはり千春らしき人物の姿などはなかった。もっとも後部座席のガラスは運転席のそれよりもっと色調の暗いフィルムが貼られているのでハッキリとは分からない。たとえば座席の足元に横倒しにして黒い布でもかぶせておけば隠すことは可能かもしれない。しかし、鞠枝はふるふると首を振った。いません、とハッキリ言う。鞠枝の声には疑いがなかった。 「……ちはる、ちゃん……」 鞠枝が呆然とつぶやく。弱々しく誰にも伝わらないような声で。なにもない後部座席をじっと見、いまにも手を付きそうなほど窓に近寄って。 吐息でガラスがくもる。これ以上、もうどこを探したらいいのか、わからない。 りん子はたまらなくなって鞠枝の横を離れた。もう一度運転席をのぞき、それからヘッドライトの前へ、助手席の横へぐるりと車体を一周する。 「ま、鞠枝ちゃん!」 と、あるものが目についてりん子は慌てて鞠枝を呼んだ。憔悴した様子の鞠枝が力なく寄ってくる。 「見て、これ。鞠枝ちゃんのと同じじゃない?」 そうして指さしたものは、後部のトランクに挟まれて垂れている赤いスカーフタイだった。それは今まさに鞠枝の胸元にあるものと同様の素材で、おそらくは。 「千春ちゃん?」 色めきだった鞠枝の表情はしかしすぐさま褪せた。眼に見えるほどハッキリと青くなりおそろしいことを悟ったように全体が引き攣る。そしてスカーフを引きちぎらん勢いで掴み、 「千春ちゃん、千春ちゃん!!」 と声を荒らげて呼んだ。 「鞠枝ちゃん落ち着いて、まだここにいると決まったわけじゃ、」 「千春ちゃん、いるなら返事して、聞こえる!?」 肩をつかんだりん子の言葉はしかし鞠枝には届いていなかった。似つかわしくない荒い息をして鞠枝はトランクに指をかけて持ち上げようとする。無論ロックがかかっていて開くことはない。ガチャ、ガチャ、と情のない音がいくたびか鳴るだけだ。 「酷い、酷い、ひどい!」 青ざめた頬の上を涙がつたう。トランクをこじ開けようとする指先は血が絶えるほど力を篭められ白くなっていた。 「どうしてこんなひどいこと! こんなところにいたら死んじゃう……千春ちゃんが死んじゃう!」 わああっと膝を折って地面につき、汚れるのも気にしないでうずくまる。指先だけがナンバープレートのあたりを何度も引っかき傷をつけた。 りん子は駐車場内にわんわんと響く鞠枝の泣き声を、少しでも響かせまいとその背をくるむようにしてなだめた。 「私たちが落ち着かなきゃなんにもならないよ! 落ち着いて、鞠枝ちゃん!」 鞠枝はしゃくり上げながら宥めるりん子の手を掴んだ。ぎゅうっと力が篭る。うすく細い肩を正面から抱きしめて、りん子は鞠枝の背を撫でた。 「なんとかして助けよう」 言うと鞠枝は、ひっく、とひとつ大きく息を吸う。その音を聞くとりん子はむしろ冷静さを取り戻した。 さてどうしたものか、とりん子は顎に手を当てる。常識的に考えてこのトランクを鍵もなしにむりやり開けることはまず不可能だろう。ならば、何らかの方法で直接三崎に交渉するしかない。だがもし本当に千春がこの中にいるのだとすればそれを承諾する可能性はまず無いと考えていい。 だとすれば方法はひとつ。三崎に罪を認めさせるよりほかは、あり得ない。  そんなふうにりん子が慣れない交渉術の手順を考えていたときである。 「何してる!」 吠えるような声が、突如駐車場内に響いた。 おどろいて二人がそちらを見やるとそこには予想だにしない人物が姿をあらわした。 「み、三崎先生……!?」 りん子は目を見開き、鞠枝はいっしゅん憎悪を滲ませたが、すぐさまそれを隠すようにくちびるを引き結んだ。 「なんだ? もしかして、鞠枝か? それに」 三崎はギロリとりん子を睨む。 「芥辺さんじゃないですか。なんなんです、こんなところで。いや。それよりもどうして鞠枝と芥辺さんが」 ぴりっと警戒する空気が三崎から漂った。緊張した面持ちでふたりをねめつける。ゆっくりと近づいてきて、大げさな身振りをしながら声を張り上げた。 「それは俺の車ですよ。これから出かけなきゃならないので、ちょっと退いてもらえませんか」 三崎は心底迷惑そうに言った。しかしりん子はその口調の中にどこか焦りのようなものが滲んでいるのを見逃さなかった。 「出かけるって、どちらへ?」 「どこだっていいでしょう。あなたには関係ない」 不愉快そうに眉を顰める。手に握っていたキーをチャリチャリと落ち着かなく鳴らし、三崎は警戒しながら近寄ってきた。応えるようにりん子も警戒を強める。よもや直接呼びだす前に三崎に会えるとは思いもしなかった。これはチャンスであり、同時にピンチでもあるのだ。 さすがに、というべきなのかどうか、鞠枝は怯えきったような目をしている。そもそもストーキング行為を受けていたのは鞠枝なのだ。いかに強気に振舞っていたとて、加害者を前にしては恐怖で身体がすくむのも当然である。りん子はさりげなく鞠枝をかばうようにして立った。 駐車場には相変わらず人気がない。ひんやりと静まりかえったそこへ三崎の靴音が大きく響く。 「それとも何か用事ですか」 カツン。カツン。一歩一歩距離を詰めてくるその間、りん子はひたすらに考える。どうしたらいい。どうしたらこのトランクを開けることができる。どうしたら千春を助けられる。 つうっと背中を汗がつたった。 「そうです。私たち、あなたに用があって」 「へえ。どんな」 思えば、三崎はあの法律事務所で向かいあったときと比べるとあきらかに強ばった声音をしている。それだけ余裕が失われているのかもしれない。触れれば弾けそうなのはどちらも同じで、膨張した空気だけがお互いを圧迫するようにせりあっている。 どうしたらいい。 心臓がますますはやくなっていた。今は誰の――悪魔たちの助けも期待できない。下手に相手を刺激しても厄介だ。 りん子は深呼吸をして三崎の手元で鈍い金属音を立てる鍵の束を見つめた。あれさえあれば。あれさえあればトランクは開く。そこに千春がいれば、それこそ言い逃れはできないだろう。しかし確証がない。こんなときベルゼブブの能力があればなんなく事は解決するのに、と地団駄を踏みたくなったとき、りん子はふと気がついた。 ――なぜ三崎はここにいるのだろう? 芥辺は三崎の職場へむかったはずだ。それも三崎に会うために。だが当の三崎はここにいる。欠勤をした、ということだろうか。 りん子は後悔をした。こんなことならば、書き置きをしてくればよかった。三崎に会えなかったとしたらおそらく芥辺は事務所へ帰ってきただろう。もしそこに書き置きがあればここまでとんできてくれたかもしれないのに。 いや、だめだ。こうしてすぐに他人に頼りきるくせはあまり褒められたものではない。芥辺の言いつけを破ってまでここへきたのだから、この場面は自らの力で切り抜けなければ。混乱しかける思考を振りはらおうとりん子は思いきり息を吸った。薄いながらもまあたらしい酸素が肺をめぐってようやく頭がいくらか冴えてくる。 必要なものは鍵。それと確証。肉体的な力の差は明らかで、それゆえに時間的余裕はそれほどない。仮に力尽くで鍵を奪いとれたとしてもほどなく取り押さえられて終わるだろう。状況的に優っている要素があるとするならそれはこちらが二人であること。無論二人合わせたところで力ではかなわない。 ならば。 「鞠枝ちゃん」 りん子は三崎に聞こえないよう声をひそめて、背後にいる鞠枝に話しかける。りん子はポケットから自分の携帯電話を抜きとるとそれを鞠枝に渡した。 「この中に事務所の番号が入ってる。芥辺探偵事務所って名前で登録されてるから、それでアクタベさんに連絡をとってほしいの」 「わたしが?」 鞠枝は首をかしげる。強ばった身体の動きはまだいくらかぎこちなかった。 「そう。私が三崎先生を引き留めておくからその間に千春ちゃんは駐車場を出て。さっき案内図を見た横にエレベーターがあったでしょう。あれで地上にあがって、おねがい」 「そんな、危険すぎます!」 「二人でここにいてもあの人から鍵を奪うことはできないよ。それにここじゃ電波が通じないの。私は大丈夫だから」 「何をごちゃごちゃやっているんですか」 三崎が不愉快そうに言った。鞠枝はおびえながらも三崎をにらむ。そして三崎の反対側――駐車場の奥のほうへと視線をやり、りん子の背でようやく立ちあがった。 「……分かりました。でも絶対に無茶はしないでください。だって三崎先生は、千春ちゃんを……」 「分かってるよ。大丈夫。さあ行って、頼んだよ」 「はい!」 威勢よく返事をしたかと思うと、鞠枝は飛ぶように駆けだした。背中にあったささやかな熱が消え失せてりん子はほんの刹那不安になる。だがすぐさま意識を引き戻した。 三崎がアッと口を開けて、何かを察したらしく鞠枝を追いかけようとする。だがその一方でりん子を捨ておくことも危険だと判断し、どう行動したものか決めかねている様子である。 力で敵わないのなら二手に分かれるしかない。りん子の選択はどうやら正解だったらしい。 「クソッ」 汚い言葉を吐いてから三崎はキッとりん子に向きなおる。 「どういうことだ、アンタ一体何者なんだ」 「心当たりがあるんじゃないですか。それより三崎さん、あなたにお願いがあるんです」 「うるさい退け! おまえに構っている暇はない!」 「そう言わずお願いします。このトランク、」 りん子はその隙間から力なく垂れている赤いスカーフタイを指さしながら三崎に向かう。ギクッとして三崎の顔面から血の気が失せていくのがわかった。 「中を見せてもらえませんか。……いえ。それよりもあのスカーフ、一体どうしたんです?」 「何を……」 「市川千春ちゃんをご存知ですね? 彼女いま、行方が分からなくなってるんですよ」 「それがどうしたっていうんだ。俺には関係ない、そこを退け」 三崎の言葉は徐々に荒さを増していた。青く引きつっていた表情が段々と血を上らせて赤くなってゆく。苛ついた足どりで距離を詰めどうにかして車に乗り込もうとしている。だがりん子が運転席のドアを塞いでいるので、それはかなわない。 チャリチャリと鳴る鍵の音を聞きながら、それ以上に大きく響く自分の心音が煩わしくてたまらなかった。あんなにも偉そうに鞠枝に言い切ったくせに実のところこんなにも恐怖している。なんて情けない。だが一応は、大人としての威厳くらい保てただろうか。 いけない。余計な思考がはたらくようになってきた。りん子は米噛みを伝う汗をぬぐい、もう一度三崎に向き直った。しかし。 「退け!」 予想外にすぐそばでその声が聞こえたかと思うと、ほとんど飛びかかるように距離を詰めてきた三崎にりん子は思いきり肩をつかまれ、振り回すように身体をひきたおされた。 「イッ……」 硬いコンクリートへ腰と肩をしたたかに打ちつける。電流の流れるようなじんじんした痛みが骨を伝って身体中に拡がった。急な回転運動でグラグラする頭を何とかまっすぐに保ち見上げると三崎が車のロックを外したところだった。 三崎はみじめたらしい恰好で慌てて車に乗り込もうとしている。りん子は這いずるように車の背後にまわり、三崎が身体を仕舞いこむより先にトランクに手を掛けた。 「おい!!」 気がついた三崎が閉めかけたドアを開いて車外へ飛び出す。三崎自身の手によってロックが解除されたおかげでトランクはカチャっという音と手応えを返し遠慮がちに開いた。りん子は乱暴にそれを持ち上げようとする。はさまっていたスカーフがはらりと落下する。その狭いトランクの中央に、横たわっているもの――。 「ち、」 「やめろ!」 ガンっという、衝撃。脳天から星がとびまわるような。視界が白くなり、ついで黒くなり、それからようやく痛覚がはたらく。痛いと思ったときにはもうりん子の身体は大きく揺れていた。軸を保てなくなりりん子は両手をトランクのふちにつく。しかしガクンと膝が折れ、りん子はその場に崩れた。 ――千春ちゃん。 奇しくもトランクをのぞきこむような恰好になり、そうして、トランクで丸くなる千春の姿が目に入った。 ようやく、見つけた。 千春は手足をガムテープで縛られた状態でトランクの中に押しこめられていた。瞼は閉じられている。気を失っているのか……。 やはり、鞠枝は正しかったのだ。千春はここにいた。泣きわめいた声が、もしかしたら届いていたのかもしれない。そう思うとりん子はますます自分が情けなくなった。こんな土壇場にきて、意識を手放そうとしている自分が。 視界のすみに三崎の靴先が見えた。だがそれももやもやと歪んでゆく。ごめん、鞠枝ちゃん、と曖昧に思う。 鞠枝は無事に地上へ上がれただろうか。そうであれば、芥辺に連絡をとれなくても責任だけは果たせただろう。大見得を切ったくせにこのざまだ。なんて恰好の悪い。意識が段々と遠のいていく。視界も狭くなりついにはなにも見えなくなった。 ごめん、鞠枝ちゃん。ごめん、千春ちゃん。ごめんなさい、アクタベさん。 ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい……。ああ、こんなところへ来る前に相談しておけばよかった。帰ってくるのを待っていればよかった。せめて行き先くらい書いておけばよかった。 もっときちんと、言うこと聞けばよかった。 悔しいのか情けないのか、あるいはただ恐ろしいだけなのか。つうっとしずくが頬を目尻をつたう。 ごめんなさい、――。 ふっと思考が途切れる直前。 それはまぼろしに違いない、けれど地上の雷鳴が、たしかに聞こえた気がした。 (続く) |