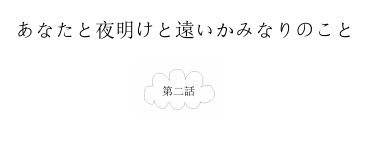 高級ホテルのロビーを思わせる待合室は時間帯のせいもあってか、しぃん、と静まり返っている。仄暗い照明に幾何文様のプリントされた灰色の絨毯、金色の柱、黒くつややかな壁などから物音を立てるたびに反響があって、場違いなところに来てしまったと己を顧みながらりん子は思った。 芥辺と並んで腰掛けている柔らかなソファは事務所にあるような簡素なものとはまるで違って、夢のような座り心地である。見事な設計によってその通風口は巧みに隠されていたがおそらくは天井から吹いてきているであろう風は少々冷えすぎていて、表の燃えるような暑さを忘れそうだった。こんな誰もいないような場所をキンキンに冷やして利などあるのだろうか。そう思いながら横を見遣るが、隣の男の表情は暑くても寒くてもあまり変わらない。 「関わるなって言ったじゃないですか」 平生どおりの自分の服装をちょっとばかり後悔しながらりん子は口を尖らせて言った。黒く光るおちこちからその声が跳ね返って戻ってくる。媒介する空気の緩衝によってそれは柔和さを増していた。 「俺一人では警戒されるだけだ」 体勢を変えないまま芥辺はずいぶんと不機嫌そうに言った。いつもの黒いスーツをまとってりん子より幾分かはましな格好をしているはずだと思うのに、彼はやはり空間になじむということがなかった。 その横顔からどうでもよさそうな、それでいて不愉快そうな気配がにじみ出ている。彼にとってこの状況はかなりどころではなく不本意なものであるらしい。私に当たらないでほしいなあと正直迷惑に思いながら、りん子は露出して冷えている腕をさすって温めた。 ベルゼブブを引っ張ってこられなかったのは芥辺にとってかなりの誤算だった。 依頼を受けた次の日、芥辺はどこから集めてきたのか例の男の情報をすでに十全に把握していた。身元捜索人用に予めつくってあるテンプレートへ情報を入力するとそのほとんどの項目に大なり小なり何かしらの記述がある。芥辺はデータを印刷してファイリングすると分厚いプラスチックのそれを鍵付きの金属棚に仕舞った。 明らかに個人情報保護法に抵触しそうなこれらの情報が一体どういう経路をたどってこの事務所に辿りつくのかは分からない。しかしたった一日でこれほど多くの情報を得られるこの人は少なくとも探偵として、一定の評価を得られていいはずである。 さていよいよ最終段階に入るというので、証拠写真を押さえる前に本人と接触しておこうということになった。ストーカー案件の難しさは立証よりも解決にある。対象者をストーカーと断定することはそれほど困難ではないのだが、行為をやめさせるためにはそれ相応の時間か、あるいは相応の暴力――それは必ずしも物理的なものであるとは限らない――が必要なのである。 依頼者の、もとい千春の望みは三崎浩一を再起不能にすることであった。再起不能という言葉には人によって解釈に幅があるとは思うが、この悪魔探偵が関与した時点で少なくとも社会的信用の失墜くらいは免れないだろう。いずれにせよ対象者を直接に伺っておくに越したことはない、それにはベルゼブブの能力があればすべて滞りなく行えるだろうというので、彼はあの開かずの間の鉄扉を開いたのだった。 ところがベルゼブブを召喚すると魔方陣から出てきたのはぐったりとやつれた瀕死のペンギンみたいな生き物だった。芥辺はしばらく死体のようなその身体を無表情で見下ろしていた。無表情なのにその背後からは不穏なオノマトペが聞こえてきそうであった。 どうしたんですか、とりん子が尋ねると、ベルゼブブは老人のような掠れた声で「食中りです」と答えた。 「うわあ、大丈夫ですか? 変な物ばっかり食べてるからそうなるんですよ」 冷たく放たれたりん子の言葉に抗言する気力も体力も無いらしいベルゼブブはうつ伏せになって倒れたまま黙っている。このまま死ぬんじゃないかと思うような衰弱ぶりだった。いつもはつややかなおしりの辺りの毛並みも乱れていて、身体はしっとりと濡れながら冷えている。生まれたての鳥の雛みたいな感じだ。気持ちの悪い手触りだなあとりん子は思った。 これでは使い物にならないというので仕方なくベルゼブブを返し、芥辺は考えあぐねてグリモアを閉じる。代わりに他の悪魔を喚ぶのかと思えば、呼ばれたのはりん子のほうだった。 「やむを得んな」 已むを得んことはないと思うのだが、当初の予定が狂ったせいか芥辺はかなり雑になっていた。使えねえ悪魔、とベルゼブブの魔方陣を消しながら彼は思っていた、多分。 不機嫌な芥辺に逆らうなどという選択肢はあってないようなものである。そして現在に至るのだが、関わるなと言った手前こうしてりん子と二人でいるのが我慢ならないらしい。そんなに不機嫌になるならひとりでやればいいのに、と思うのと、芥辺一人では警戒されるという論の明らかさはりん子の中でせめぎ合っていた。 「遅いですねえ」 広い廊下に点々と置かれている、絢爛な花瓶を眺めながらりん子は呟いた。こうも長く放っておかれるとなんだか眠くなってくる。仕事中だということを忘れてうとうとしだしたころに、芥辺は思い出したように言った。 「ああそうだ。さくまさん、これからここを出るまで俺に敬語は禁止だから」 「は、はぁ!?」 びっくりして一気に覚醒する。意味のわからないことを言われたと、それだけはよく分かった。 「た、タメ口きけって言うんですか?」 「そうだ。それも親しそうにしろ。余計なことは言わず、必要なときには話を合わせろ」 「むむむむりむりむりですよ!」 りん子は両手と首を千切れんばかりの勢いで振った。 そう、無理に決まっている。この男相手に親しみを持つことなど世界中の誰にもやってのけられない大仕事だ。それをこうもあっさり要求してくるとは、彼は自分という人間を分かっていないのだろうか! 「芥辺様、お待たせしました」 目を白黒させているところでそう呼ばれ、芥辺はすっと立ち上がった。 「とにかく、そうしろ。さくまさん演技は得意だろう、苺の戦士?」 「や、やめてください!」 陰険ですよアクタベさん、と語気を荒くしても芥辺は興味もなさそうにスーツの襟を正すだけだった。もっとなにか言ってやろうと構えたところへ芥辺様、ともう一度声をかけられ、りん子は嫌々ソファを立った。 「ご相談ありがとうございます。ワイ・エー・ジー法律事務所の弁護士の三崎です」 案内されたのは小ぢんまりとした、しかしきちんと高級感のある一室だった。ここはどちらかというとオフィスの社長室みたいだとりん子は思う。広さにしてあの探偵事務所ほどもありはしないが掛けている金額なら十倍は下らないだろう。とこれは根拠のない推察だ。 「よろしくお願いします」 芥辺が差し出された名刺を丁寧に受け取って頭を下げるのでりん子も倣う。そうすると三崎と名乗った彼――今回の調査対象件餌食であるところの男は笑顔でりん子にも名刺を渡した。 三崎浩一という男は、確かに奇妙なところのある人物だった。差し出された名刺を受け取りながらりん子はその顔を黙って窺う。千春の怒った顔と鞠枝の淋しげな横顔を思い出し、若干の嫌悪感を滲ませながら観察すると、理由は分からない、けれどたしかな”既視感”がそこにあった。 実際のところそれは不可解な感覚だった。 彼の姿、といってもいいのかどうか、それを見たのは鞠枝が差し出したあの写真の中のワンショットのみである。そこに千春曰くの『ロリコンストーカーの変態クズ野郎』という情報を付加されて、りん子の中でこの男はすでに立派な犯罪者に仕立て上げられていた。 しかし実際目にした三崎は、無害というほど無害ではないが有害というほど有害ではなさそうな、実に模範的な人物に見えた。大手事務所に勤める弁護士というだけあって身なりは清潔だったし、言葉や態度にもこれといって特筆すべきところがない。すっきりとした髪型はいかにも好青年然としていて、皮膚の若い感じや目鼻立ちの整った、それでいて人を魅了しすぎない感じが、彼を無個性の中に埋没させている。 どこにいてもおかしくはない。百人集めれば一人はいるだろうというこの典型的な男に既視感を覚えるのは道理といえば道理だった。しかしりん子が感じているのはそういう中途半端な感覚ではないのだ。一度見た夢を反復するときのあの、明瞭で澄みきったデジャ・ヴュ。この人を確かにどこかで見たことがあると、りん子は思った。 どこで見たのだろう。どこで会ったのだろう。どういうふうに、自分と関わったのだろう。しかしそれはまるであの夢の続きのように、靄がかって思い出すことはできなかった。 りん子がそんな思考に沈んでいる間にも、芥辺はすらすらとよくできたつくり話をでっち上げていた。曰く多重債務で二進も三進もいかなくなっただの債務整理をお願いしたいだの出来れば過払い金返還請求をしたいだの、どちらかといえば取り立て屋と言われたほうが頷けるような面をしてよくもまあぬけぬけとこんなことが言えたものである。 三崎は真剣な顔をしてうんうんと頷きながら芥辺の話を至極真面目に聞いていた。 実際こういう相談は少なくないのだろう。慣れた様子でそれならば身分証明証と債権者一覧表を用意してくださいとか手続きには陳述書と資産目録が必要ですとか、そういえば大学の授業で聞いたことのあるような単語がいくつか飛び出して、なるほど確かにこの男はこの法律事務所で仕事をまっとうしているらしいと分かった。ああ、だのええ、だの、芥辺が適当な相槌を打つのに、受任までの流れ、請求手続きに必要な書類などについて詳しく説明し、熱心で根気のある弁護士然として三崎は驚くほど丁寧に振舞った。 ひと通り説明を終えたところで、 「ところで、失礼ですがそちらの方は?」 と突然話題がりん子に向いたので、 「へ?」 とつい間抜けな声を漏らしてしまった。三崎はりん子の容姿をちょっと不躾にたしかめ、不思議そうにしている。たしかに今の話ではりん子がここにいる意図がわからない。話を合わせろとは言われたものの、どう応えたものかとあぐねていると、ああ、と、りん子が隣にいることに今気がついたようなどうでもよさそうな声が聞こえる。 「妹です」 「い?!」 予想だにしていなかった設定が飛び出したのでりん子は思わず叫んでしまった。それどころか、座っていた椅子から腰が浮きかけたくらいだ。 「どうした?」 調はやわらかだったがするどく睨まれて、あるいは凄まれて、硬い動きのままそっと腰を戻す。話を合わせろと言ったよな、と光る彼のまなざしはそう言っていた。ぎこちなく微笑を返すにとどめてあとは黙っていることにする。余計なことは言わないほうが身のため、というより、余計なことを言える余裕などありはしなかった。 「イエ……なにも」 なるほど、敬語を使うなというのはこういう訳だったわけか。ようやく合点がいったが、芥辺には言葉が足りないのだとりん子は責めてやりたい気持ちになった。 「こいつは大学で法学を学んでましてね。弁護士事務所を訪ねると言ったら一緒に行くと言ってきかなくて」 「ああ、なるほど」 どっちにしたってりん子がここにいることは不自然な気もするが、三崎はそれ以上は何も言わなかった。 代わりにこの法律事務所の顧客満足度だとか裁判実績だとか、そういうことを営業マンよろしくマニュアル通りらしい言葉遣いで説明しきると、 「おや、申し訳ありません、そろそろ時間ですね」 と腕時計を見て言った。そして広げていたパンフレットやらを纏め静かに席を立つ。 「今回は無料相談ということでしたが、もしご依頼いただけるようでしたら先ほど申し上げたとおり書類を揃えてもう一度いらしてください。受任手続きが完了すればそれほど時間もかからず、身軽になれると思いますよ」 「ええ、どうもありがとうございます」 芥辺は普段どおりの無表情で大した感動もなさそうにそう言って自分も席を立った。 「それでは」 長い廊下を歩いてもといた待合室まで二人を案内し、三崎は事務所のパンフレットを手渡して深々と頭を下げるとまた、どこへともなく歩き去っていった。 拡がりはじめた雲のおかげで予想していたほどには気温が上がらなかった午后の道を、事務所に向かってとぼとぼ歩く。荘厳な法律事務所を背にりん子は、あの寒いほどの冷気と異界のような整った内装とを思い出していた。 「あの……やっぱり私必要なかったんじゃ」 「言っただろう。さくまさんには足元を見られる才能がある」 「言ってませんよ。なんですかそれ、失礼な」 先刻の奇妙な面談について言い及ぶと相変わらずのどうでもよさそうな声で芥辺は応えた。手にはワイ・エー・ジー法律事務所の分厚い案内パンフレットが入ったプラスチック袋が提げられていて時折頼りなく揺れた。 「それにしても、あのひと本当にストーキングなんかするでしょうか。すっごく普通っていうか、むしろいい人じゃないですか」 「それこそ前にも言ったはずだ。聖人君子なんてどこにもいない。表の顔が善良であればあるほど、腹ン中に抱えてるもんは真っ黒に汚れきってたりするものだと」 「はあ……そういうものなんでしょうか」 翳っていてもアスファルトの路上はむんっと蒸し暑かった。りん子は数歩ごとに垂れてくる汗を拭いぬぐい、芥辺の持論であるらしい性悪説的人間論を適当に肯定した。 人間を嫌いになるような目にでも遭ったのだろうかと思うほどハッキリと、彼は善人を否定する。信じることが悪であるかのように、信じる者が悪であるかのように、目を養え、相手を疑えとしきりに言う。たとえばりん子が馬鹿な失敗をするたびにそれはしつこくくり返された。 りん子とて、別段他人を信じきっているというわけでもない。今日まで、ことこのアルバイトを初めてからというもの、他人に裏切られることはしばしばあった。依頼料を渋られたり面倒を押し付けられたり、そんなことを幾度も経験すればいい加減学習もしてくる。 それでもりん子には疑うということが億劫でたまらないのだ。目を光らせ神経を尖らせ、そうまでして相手の真意を探るという行為が、駆け引きが、騙し合いが、鬱陶しくてたまらないのだ。そんなことをするくらいなら初めから信頼も疑心も持たないほうがいい。その結果が利であれ害であれ、それは仕方のないことだと思っていた。金銭的な損失があれば悔しくも思うが、それだって身を挺して阻もうという気には、どうしてもなれなかった。 ――佐隈さんのそういうところ、嫌いだな。 そう言われたことがある。りん子だってこれが己の欠陥だということくらいちゃんと自覚もしていた。それでも直らない。直せない。ならば抱えて生きていくしかないじゃないかと、りん子は諦め、開き直って今日まできた。 黙り込んだりん子の横で、芥辺もまた黙っている。何も言おうとはしない。白かった曇り空が徐々に暗さを増して、もしかしたら雨になるのかもしれないと、りん子は思った。  逃げなさい、と言われていた。 次に会ったら逃げなさい。絶対に言葉を交わしたりしたらダメよ、とにかく走って逃げなさい。そう言われていた。 だから走ったのだ。この人から離れなければいけないと思ってひたすらに走った。汗がだらだら流れてきて時々眼鏡が曇ったりした。それでも止まらずに遠くへ行こうと思った。 怖かった。あの人がではなく、逃げなかったらどれだけ叱られるだろうと思った。母との約束は絶対で、破ればきついお説教が待っているのだと、あのときはその強迫観念に駆られていたのだ。 ――りん子は逃げた。たしかに、逃げた。 気がつくと、記憶は森の中へと飛躍んでいる。逃げた先が森だったのか、同じように暑く息切れてこれ以上は進めないと思うような苦しさだった。 緑の蔭がざざざ……と揺れている。相変わらず両足を動かしてはいたが、記憶の接続が上手くいっていない。いつの間に森に入ったのか、いまどこへ向かっているのか。それも覚えていない。 でも森に入るまではなかったはずの空洞が、りん子の中にあった。空洞は暗く淀んだ底なし沼のようだった。りん子はおそろしくなってぎゅっと目をつむる。空洞に呑まれないようきつく。 ここにあったはずのものは、なんだったのだろう。 ――わからない。 ここにあったはずのものは、どこへいったのだろう。 ――わからない。 だけどひどく、かなしかった。  「あれ、芥辺さんじゃないですか」 帰宅途中の新宿駅でそんな声が聞こえたのでりん子は思わず振り返った。時刻は夜の八時を回っていたが、辺りを鬱陶しく包む湿気のせいでいっこう過ごしやすくなる気配はない、夜のことだ。早く帰ってクーラーを効かせ冷たい飲み物でも飲みたいとそう思っていたところへ、それは聞きなれた珍しい苗字を呼ぶ声に対する反射的な行動だった。 「芥辺さん、ですよね?」 「わ、私ですか?!」 だから声の主がりん子を呼んでいるらしいことに気がついたとき、思わず大きな声で尋ね返してしまった。 「先日はどうも。ほら、ワイ・エー・ジーの……」 「あっ、三崎さん?」 「そうですそうです。こんなところでお会いするなんて奇遇ですね」 三崎は例によって人好きのする笑みで言うと、それから二三歩距離を詰める。りん子は後ずさりしたい衝動に駆られたが紳士的な態度を取る男の手前それは我慢した。 「いやほんと、すごい偶然だなあ。今日お兄さんは?」 「おにいさん……は、仕事です。というかいつも一緒にいるわけじゃないですし」 「まあ、それはそうですよね」 つまりこういうことだ。芥辺はあの時芥辺と名乗った、その上でりん子を妹だと紹介したために、三崎の中でりん子の姓は芥辺であるという認識なのだ。当然の論理展開だと思うが、お兄さんとか芥辺さんとか、正直すごくやめてほしい。かといってそれを訂正するのも話をややこしくするだけなのでりん子は居心地の悪さを黙って耐えていた。 「お食事はもう済みました? 僕はこれからなんですが、よかったら一緒にどうです。奢りますよ」 「食事、ですか」 持ちかけられた意外な提案に、りん子はうっと悩んだ。なにしろ相手はストーカー嫌疑の掛かっている男である。普段ならばまず間違いなく相手にしないのだが、今回はすこし事情が違っている。何故ならこの案件は現在鋭意捜査中なのである。得られる情報なら多いに越したことはないし、それに。 「じゃあ、ご馳走になっちゃおうかな」 あの妙な感覚のことが気になっていた。もしもこのまますべてを芥辺に任せていたら、この男と接触する機会は得られないだろう。そうすればあの既視感の正体を掴むチャンスもまた得られなくなるのだ。 一度きりでいい。もしもそれで分からないのなら、諦めよう。そう思ってりん子は相変わらず完璧な好青年を演じる三崎の案内に従った。 三崎が選んだのはごくごく普通のイタリアンレストランだった。小洒落た店内を橙色の照明が柔らかく照らしている。テーブルには赤いクロスがかけられ、その中央にちいさなキャンドルが置かれていた。従業員に案内されて一番奥の窓際の席につくとグラスに瓶入りのミネラルウォーターが注がれる。キャンドルのゆらゆらした灯火に澄んだ水が美しく光った。 この店の常連であるらしい三崎は小慣れた様子で料理を注文した。芥辺さんお酒は、と尋ねられ、りん子は飲みたいのをぐっと我慢して水で構わないと答える。店内に小気味良く響く食器のぶつかり合う音をバックに、そういえば男の人と二人で食事なんて本当に久々だと、今更ながらに落ち着かなくなった。 ミネラルウォーターの入った背の低いグラスとスパークリングワインの繊細で宝石のように光るグラスとをちょっと触れさせてチンと鳴らす。居心地の悪さは増す一方でりん子は水をぐいぐい飲んだ。 「その後、債務整理の件はどうなりました?」 「さあ、あまり詳しくは聞いていないので……」 「そうですか。またいつでもいらしてくださいとお伝え下さい」 「ハイ、ありがとうございます」 三崎はニコニコしている。またぐいっとグラスを傾けるといい飲みっぷりですねと笑って茶化した。 「そういえば芥辺さんは法学部に通っているんですよね。いま、何年生ですか」 「……二年です。もうすぐゼミが始まるんですが、授業にもなかなかついていけてなくて」 「アハハ。僕も学部生の頃はそんなものでしたよ。ロクに授業にも出ないでアルバイトばかりしていました。まともに法律の知識を学んだのなんてロースクールに行ってからじゃないかな」 「アルバイト? どんなバイトなさってたんですか?」 「色々やりましたよ。まあでも、家庭教師が一番長かったかなあ」 「家庭教師、ですか」 つらりと言ってのける三崎には欠片ほども不自然なところがない。相変わらず普通で、相変わらずまともそうである。なんだか面倒になってそれ以上の追求をやめ、ぼんやりと窓の外を眺めると、ほとんど店内の明かりが反射して見えたものではなかったがそれでもちらほらと街灯が見える。その下を急ぎ足で帰る人があり、もう帰りたいな、とずいぶん身勝手なことを思った。 そもそも男の人って、ちょっと苦手なのだ。 昔からそうだった。中学生や高校生の頃から、もちろん興味がまるでなかったわけではない。アザゼルは処女処女と自分をからかうし、事実そうなのだけれど、だからといっていわゆる彼氏という存在が一度もいなかったわけではない。中学生の頃、クラスメイトの男の子に好きだと言われ、断るのが億劫だったので付き合ってみたら、しかし相手は変態だった。おぞましいことを要求され気持ち悪いから別れてくれと告げると、次の日にはクラス中に佐隈りん子はビッチだとふれ回られて、しばらくは学校にいくのが本当に苦痛だった。二人目の時、それでも高校に進学しそんな過去を忘れるためにもと思って付き合った相手がまたもや変態だと分かって、もうやめようとりん子は思った。碌なことがないから、誰彼構わず受け入れるのはやめようと。そうしたら色んなことがどうでもよくなって、自然言い寄られることもほとんどなくなった。 そう考えてみると、芥辺は不思議な存在だった。あの狭い空間にたとえば悪魔も光太郎もいなくてふたりきりだったとしても、息が詰まるということはほとんどない。不機嫌なときの彼はたしかに恐ろしいが、だからといって不快だとか鬱陶しいとか、そんなふうに思うことはなかった。 アクタベさんって生きてる感じがしないからかなあ。りん子はあの表情の乏しい男の姿を思い出し、彼に生き物の匂いがほんのすこしもしないことについて考えていた。 「芥辺さん?」 と、三崎が黙り込んだりん子を気遣わしげに呼んだ。この無個性らしい男からも、しかし確かににおいがする。生き物の、人間の、生々しいにおい。女は普通、これに惹かれてしまうのだろう。 「どうかしました? 料理、きましたよ」 「え、ああ。いやなんでもないです。頂いてもいいですか」 「もちろんどうぞ。芥辺さん、茄子はお好きですか。ここのパスタはこの茄子とトマトのがいっとう美味いんですよ」 三崎は小皿にパスタとピザをそれぞれ盛るとりん子に差し出した。粗めのパルメザンチーズがのっている、トマトソースの絡んだパスタはたしかにきらきらとして、見目もいい。おいしそう、とつぶやきながらりん子はそれを受け取ってフォークを手にした。 「……ところであのー、そのですね、あ、アクタベさんっていうの、やめてもらえませんか」 フォークに絡ませたパスタを再び皿に下ろして、りん子はすこしばかり思いつめたように言った。 「え?」 「あ、いや、違いますよ、別にファーストネームで呼べとか言ってるわけじゃないですよ、なんていうか、つまりその……」 「なんです?」 三崎は怪訝そうに、りん子の言葉の真意をはかりかねた顔をしている。当然だ。りん子はなにか上手い説得方法はないかと考えたが、芥辺が妹だと紹介したことに矛盾しないつくり話は咄嗟には出てこない。 「……ううん、複雑なんです。まあいいや……いいか……すみませんやっぱりいいです、アクタベでいいです」 私は芥辺、芥辺りん子……。 りん子はぶつぶつと口の中で唱えながら、それはない、それはないなと拭えない違和感を持て余した。 「アハハ、芥辺さんは面白いですね」 「……ああ、どうも……」 せめてもう呼ばないでほしいと思いながら、りん子は絶品パスタを頬張ってそれ以上は諦めることにした。 結局それから店を出るまでほとんど当たり障りのない話だけをして、彼に関する新しい情報も、あのデジャ・ヴュの正体も、何一つ得ることができなかった。会計をしてもらって店を出、新宿から家に帰ってりん子は、犯罪者かもしれない男に食事をおごってもらったという、変に後ろめたい事実だけを作ってしまったのだと考えてなんだか妙に落ち込んだ。  「でね、アクタベさん。だから一応三崎さん本人の口から”アルバイトで家庭教師をしてた”って話は聞けたんですけど」 話すかどうかを迷ったが、りん子は次の日芥辺に、三崎と食事をしたことを告げた。 朝からどんよりと曇った空の下はほとんど百パーセントに近いくらいの高い湿度を保っていて、いつ降りだしてもおかしくないような天気だった。窓から見えるビル群の遠くのほうが霞んでいて、街が水に沈んでいると思うくらいに息苦しい。 芥辺はひどく顔を顰めて責めるようにりん子を見た。ベルゼブブの病状報告のために喚び出され、事務所のソファで漫画を読んでいたアザゼルがニヤニヤしながらからかうように、 「ストーカーと飯とか、なんぼ男に飢えとるからってそらないわ。これやから処女はいややねん」 と言った。りん子はむっとしてこれに反論する。 「違いますよ、私はただちょっとでも情報が得られればいいなって思って……」 何故か言い訳するように芥辺の方を向いて言うと、黙っていた芥辺はパタン、と読みさしの本を閉じて、りん子をおそろしい形相で睨んだ。 「関わるなと言ったはずだよな?」 低く問いかける芥辺の表情に黒いものが漂った。ビクっとアザゼルが肩を揺らす。漫画をテーブルに置いて逃げるようにそろそろとドアに近寄っていった。りん子にしても、震えこそしなかったが正視にたえなくて思わず視線を逸らしてしまう。 「だ、だってそれは、ベルゼブブさんがいれば私の手は必要ないって話だったじゃないですか」 怯みながらも何とか口にした言葉は、けれども芥辺の静かな怒りを、どうやらわずかに加速させた。 「そうじゃないだろう。いや、仮にそうだったとしても、あの男と二人で食事をするなんてどうかしている」 「たまたま会ったんですよ、それで誘われて」 「大方奢りだとか言われてついていったんだろう。なんの警戒もなくふらふらと」 「そ、そんなんじゃありません! 私は、こんなチャンスはないと思って……」 「さくまさんには、危機感が足りない」 ふらりと、芥辺は立ち上がった。その動きがあまりにも妖しくてりん子は思わず一歩後退する。 「そりゃ、大した情報は得られませんでしたけど、でも」 「いい加減にしろ。命令をきけないならもう来なくていい」 冷たく言い放たれた言葉にきゅっと肩をすくめた。 「な、何をそんなに怒ってるんですか……?」 おそるおそる尋ねても、芥辺は答えなかった。ただ体の芯から震えあがるような怒りの空気だけがぞわりぞわりと肌を粟立たせる。こんなにも静かに怒る芥辺は珍しく、しかもその矛先がりん子に向くことはもっと珍しかった。 芥辺がもう一歩にじり寄ると、同時にゴロゴロゴロ……と遠くのほうで雷が鳴りはじめる。雨はまだ降っていなかったが、その不穏な気配がたしかに忍び寄ってきている。そのいずれにか、ヒッと小さく悲鳴をあげてりん子は耳をふさいだ。 「すみませんでした……も、もうしません。だからクビにはしないでください」 りん子が懇願するように言うと、ガンッと思いきり壁を蹴って、芥辺は短く「そうしろ」とだけ言った。 雨雲に乗った低い雷鳴が、遠くから、地を這うようにやってくる。 (続く) |