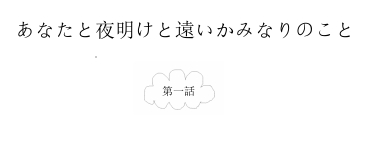 暑さで、頭がぼうっとする。 ジャワジャワと降ってくる蝉の声と、生ぬるい風に吹かれてさんざめく緑の蔭。それに合わせて太陽の光があらわれたり消えたりする。チカチカ、眩しい。 もうどのくらい歩いたんだろう。足が疲れて先程から頻繁にもつれている。すりむいた手のひらから薄く血が滲んでいた。転びかけたとき傍らにあった樹の幹へ手をついたからだ。たくさんの汗が米噛や、ひたいや背中を伝う。ワンピースの薄い布が身体にぴったりと貼りついていたし靴下は土でよごれていた。 道に積もった植物の絨毯に足をとられるけれど、でもここが上り坂とかじゃなくてよかった。もしそうだったらきっともう歩けないってうずくまっていただろうから。そうしたら前にも後にも進めなくなって、ここから永遠に出られない。お父さんにもお母さんにももう会えない。仕方ないかなあって思うけど、本当はそれは嫌だ。 空を見上げると木木の間を一羽の鳥が横切った。視界ははっきりしていて、眼に見えるものは見えすぎているくらいだ。 それなのに頭の中には靄がかかってすべてが曖昧だった。いや、曖昧というより何かがぽっかりと抜け落ちて、穴を埋めるように、辻褄をあわせるように、そこへ思考の川が流入しているような感覚だった。 なにか考えなくてはと思うほどなにも考えられなくなる。燃える昼日に頭をぐるぐると引っかきまわされて、そうすると何もかもがどうでもよくなった。 ――あるきつづけよう。 それだけを、ハッキリ思う。 歩き続けよう。ついていこう。置いていかれないようにしよう。 そしてこの森を、たしかに出よう。 今はそのことだけがどこかかたくなに、頼りない二本の足をがむしゃらに動かしていた。強ばっていきそうなそれをどうにか叱咤して止めないようにしていた。だらだらと汗が流れて呼吸が苦しくなっても、身体が重みをうしなって、わけのわからないカラッポをそこに感じても。 ふと。 ふと、前を進んでいた影がふりかえり、ゆっくりとちかづいてきて太陽をさえぎった。眩しかったのがやわらいだのでほっと息を吐く。 「――」 影は何かを言った。のろいの言葉かもしれない、と思った。 でもふしぎと怖くはない。ゆらゆら揺れる船の上にいるみたい。大きくて、おだやかで、やさしいかんじ。 何を言ったんだろう。 あなたは、だれだったんだろう。  「ユメぇ?」 夏の盛りの、午后のことだ。 事務所のソファに腰掛けて、りん子と光太郎はアイスキャンディーをなめている。光太郎の背にはいつもの通りグシオンの姿があるが、アザゼルやベルゼブブを喚び出すような用事もなく、室内は比較的ひっそりとしていて静かだった。 ペンキを塗りたくったような真っ青な空に積乱雲が猛っている。太陽が濃灰色のアスファルトを灼き、そこから立ちのぼる水が雨上がりに似た匂いを放っていた。冷房の効いた事務所の中でさえ放っておくとあっという間に融けてしまうアイスを器用に小さくしていきながら、光太郎と二人、気の遠くなるような数字を映し出すテレビの気象予報を見ていた。そこでりん子は思い出したように――事実そのことをふと思い出して、唐突に言った。 「そう、夢。ここのところ毎日なんだよねえ。子供の頃の夢」 「子供の頃って。ねーちゃんって時々ババくせぇよなあ……イデデデデ」 「キミは口の悪いとこをなおした方がいいねえ」 向かいのソファから身を乗りだして耳を吊りあげてくる細いくせにびくともしない腕へタップを入れて、ギブギブ、と光太郎は中腰になってわめいた。りん子はパッと指を開いて解放し「教育的指導」と短く宣言する。右耳をさすっている後ろでグシオンがどうしたのだコータロー耳が痛むのか、などと尋ねてくるのに、いま引っ張られたんだよ見てなかったのかよと律儀に応答していた。 「だいたいそんなこと俺に言ってどうすんだよ」 「別にどうも? ただ思い出しただけ」 りん子がしれっと言うので光太郎はうらめしそうな顔をする。 「そういうことってある? おんなじ夢を何回も見るみたいな」 「ないね」 「ああ、光太郎君の場合はいっつもエッチな夢だもんね」 「うっせえな、結局何が言いたいんだよアンタ」 「だから別に何も。ただ」 暇なんだよ、と幾許か声を小さくしてりん子は窓際の男に視線を遣った。 依頼人はない。任されていた事務処理も午前のうちに片付け終わっていたので、本当にやることがなかった。しかし生憎とこのアルバイトは日給制である。早めに切りあげて帰るわけにもいかず、学校から帰ってきたばかりの光太郎を誘ってコンビニへ行きアイスを買う。そのくらいの自由は許されていたが、しかし終業予定時刻まではまだかなりの時間があった。 男――芥辺はいつもと同じにあの玉座みたいなチェアにすこし斜になって腰掛け、分厚い本のページを黙々とめくっている。椅子の軋むわずかな音と紙の掠りあう音を立てることはあってもあとはほとんど無音と言ってもいい。夏だというに黒いスーツをジャケットまでしっかり着用して当人は涼しい顔をしている。しかしそこから放たれる言いようのない威圧感が、むしろ室内の温度を高めているような気がりん子にはした。 「アクタベさんは子供の頃の夢をみること、あります?」 アイスキャンディーの最後のひとかけを一気に口に含んで、その内側の熱ですっかり融かしてしまうと裸になった棒を袋に放りこむとりん子は芥辺へと振りかえって尋ねた。 「……ない」 「ですよねえ」 振っておいてなんなのだが、そもそも芥辺の子供の頃というのがりん子には想像できない。この悪魔のような男に天使のような年頃など存在したのだろうか。というか両親が存在するのかそれすらあやしい。いや、健在か否かはさておいて、いないはずはないと思うのだが。 「でもそっかあ。やっぱないですよね。私もここ最近なんですよ、イキナリ」 彼がまともな答えを返してくれたのが意外で、りん子はすこし嬉しくなりながらひとりごとのように言った。 物怖じしないのは自分の長所だと思っている。相手が誰でもそれなりに対等に会話ができるというのはくさぐさの場面で結構役に立つ。ことこの探偵事務所でアルバイトとして勤めるには、それなりどころかもっとも重要な能力だったのではないかと思うくらいだ。そういえばこのことは光太郎にも共通して言える。彼もまた人を選ばない、言いかえればどの他人も等しく他人として扱える、いくらか特殊な人間だった。 「どんな夢なんだ」 「え?」 「だから、どんな夢を見るんだ。子供の頃のって」 意外、だった。ほとんど暇つぶしのために振ったような話題に彼が興味をもったことは。こちらを向いた芥辺に手元の本がパタンと閉じられて――栞もはさまずにそうしてしまってよいのだろうか、と思いながらもりん子は、あのつまらない映画のワンシーンのような夢を反芻する。 「すごく、ぼんやりとしてるんですけど。今日みたいな暑い日に、小さいころの私が森の中をひたすら歩く夢です」 森の蔭。葉のかたち、枝のするどさ。緑の絨毯、鳥、蝉の声。 汗ばんだ身体の不快感、それと同時にある虚脱感。 靄がかったそれらすべてを思い出す、描く。けれどもやはり曖昧だった。たしかにくり返し見ているのに、その細部はちっとも思い出されない。 「でも覚えのない場所なんですよね。行ったこともないような」 「なんだソレ。くっらい夢……デデデデだから耳を引っ張るなよ!」 「学習しようね」 性懲りもなく失礼な反応を見せる光太郎に制裁を加えてから、たしかにあれは暗い夢だと、りん子は思った。 くり返し見る夢は何かの暗示だという人がある。深層心理なんていうのはまだましな方で、警告だとか前世だとかはたまた未来予知だとか、ずいぶんとまあ突拍子も無いことを思いつくものだと感心するものだが、そういうのは馬鹿々々しいと切って棄ててきた身だから大げさに騒いだりする気にもならない。しかし引っかかるといえば、たしかに引っかかる。こんなことははじめてだった。 「でもさ、一度も見たことのないものは夢には出てこないって言うじゃん。知らない場所や人のように思えてもそれは忘れてるだけで、たとえば旅先とかテレビとか、必ずどっかで見たことのあるもんなんだって」 光太郎がやや警戒しながら――耳をかばうような素振りを見せながらすこし控えめに、言う。 「だからねーちゃんのそれもたぶん」 「忘れてるだけ、かあ」 りん子はソファの背に凭れかかって光太郎の言葉を反芻した。自分で聞いたくせに芥辺はすでに興味を失っているらしく、何かを考え込んで、もうりん子の話など耳には入っていないようだった。りん子はため息をついた。 窓の外の夏雲がもうもうと形を変える。午后も暑くなりそうだ。太陽が顔を出して、室内はにわかに明るさを増した。  その依頼人がやって来たとき、芥辺探偵事務所ではほんの一瞬時が止まった。ゲーセン行ってくるわと言い残して光太郎が事務所を出ていってから、それは三十分も経っていなかった。芥辺とりん子、二人の視線が古びたドアに集中して注がれいくつものまたたきが生まれる。あの芥辺ですら面食らった顔をしたので、りん子の驚愕など推して知るべしである。彼女たちがどこか別の場所と間違えてその扉を開けたのだと咄嗟に思ったくらいだった。 そうしていると扉を開けた依頼人――セーラー服をまとった二人の少女のうち、長い髪を高い位置で括った勝ち気そうな少女が「おはなし、聞いてもらえますか」と口火を切った。それでようやく凍りついていたものが融け、りん子は芥辺を窺った。 アザゼルを召喚していなくて良かったとりん子は思った。セーラー服の少女だなんて彼は大好物に決まっている。そうすれば血を見るのは明らかで、りん子に振りかかる面倒も倍くらいにはなっただろう。 少女二人に対し、芥辺は一瞬だけためらう素振りを見せた。しかしやがて、とりあえず入ってもらってといつもの口調で言う。遠慮がちに開かれていたドアを大きく押し開けて、りん子は二人を中へ入るよう促した。 少女たちは悪魔の根城たる芥辺探偵事務所に踏みいってくる。変な胸騒ぎがした。 「それで」 ソファに掛けた依頼人と向きあって、芥辺はずいぶんと素っ気ない口振りで訊ねる。陰の気をあおるいつもの営業口調があらわれないのをみてこれは乗り気じゃないんだなとりん子は思った。それもそのはず、彼女たちはいかにも善良な女子高生であり、この薄汚れた雑居ビルにはどう考えてもそぐわない。まして”悪魔探偵”などという怪しい看板を掲げるこの事務所の門戸を叩くにはあまりにも清浄すぎていた。 「私は市川千春といいます。この子は笠原鞠枝。ふたりとも藤山高校の二年です」 ポニーテールの少女――市川千春はその大きく意志の強そうな目で怯みもせずに芥辺を見据え、ハッキリとした声で名乗る。その横で笠原鞠枝は、肩下におりている細く真直ぐな髪を不安気に揺らした。 紹介されて頭を下げた鞠枝は、千春とは対照的に髪も肌も色素がうすく、やせた手足が頼りないはかなげな少女だった。千春がどこか挑むように身を乗り出しているのを落ち着かない様子で見ている。二人の関係はひとめで見てとれた。そんな鞠枝の気遣いもおかまいなしに、千春はハキハキと、すこし怒ったように言葉を続けた。 「実はこの子、ストーカーの被害に遭っているんです」 「ストーカー?」 りん子が反覆したのに、鞠枝は申し訳なさそうに目を伏せる。千春に促されて鞠枝は脇に置いていた学生鞄から一枚の写真を取り出すとそれをおずおずとテーブルの上に差し出した。 「これは?」 「犯人です」 「ちょっと、千春ちゃん」 「いまさら隠すこともないでしょ。このひと、むかし鞠枝と付き合ってた男なんです」 鞠枝のわずかな躊躇と抵抗を軽くたしなめて向き直り、テーブルの上の写真へ憎々しげな視線を送る。人間のクズみたいなヤローです、と千春は攻撃的に言った。 ストーカーなどというものだから絵に描いたような変態、というのも可笑しな話だが、たとえばいつかのような太って脂ぎった中年男性だとか、色白でキレやすそうなやつだとかを想像していた。しかし実際差し出された写真を覗きこむと、そこへ写っていたのはどちらかといえばむしろ好青年とでも呼べそうな、正義に満ち溢れた表情をした男だった。 「この男の名前は三崎浩一。かつては鞠枝と私の共通の家庭教師でした」 千春は男についての情報をよどみなく話した。歳は二八で独身、業界最大手のワイ・エー・ジー法律事務所に勤める弁護士だという。なるほど、ますます写真の中の余裕の笑みが深まった気がしてくる。ここが探偵事務所などでなければ見合い相手の優良物件を紹介されてでもいるかのようだった。 「ワイ・エー・ジーって、あの?」 「知ってるんですか?」 「こう見えても私、法学部生なんだ。ワイ・エー・ジーって言えばトップクラスの就職先だよ。あなたたち高校生でいうところの、東大とか京大みたいなものかな」 りん子の言葉に小さくうなずいて千春は続けた。 「この人が私たちの家庭教師をしていたのは法科大学院に通っていた間の二年間です。私たちは当時まだ中学生でした」 「中学生……」 「そう。この男はロリコンストーカーの変態クズ野郎なんです」 「千春ちゃん、言い過ぎよ」 「言い過ぎ!? どこが言い過ぎ? あいつはサイテーだよ、あんなやつに勉強を教わっていたのかと思うと吐き気がする」 息巻いて千春が言うと鞠枝は困ったような顔をした。それもそうだろう。昔の男のことを――それも共通の知り合いである男のことをここまで滅茶苦茶に言われては彼女も立つ瀬がない。責められているのは男でも、鞠枝が自分まで非難されているように感じるのは道理である。それくらい千春の口調は断定的で、攻撃的だった。 「それで、ストーカーというのは」 男のひととなりにはそれほど興味がないらしく黙りこくっていた芥辺が本題をというように切り出す。千春は鞠枝を突付いて言葉を促した。 「……はじめは、気のせいかとも思ったんですけど……」 芥辺の無言の圧力に気圧されてか、鞠枝がためらいがちに話す。鞠枝の容姿に似合ってその声もまた細くたよりない。何かに怯えるような瞳はあちこちに揺れておぼつかなかった。 「視線を感じたんです。登下校のとき、友達と買い物に出ているとき、自分の部屋にいるとき……いつも、ではありませんでした。でも確かに誰かにみられているという感じがして」 話しだすと鞠枝の表情が徐々に曇っていくのがわかった。今まさに何者かに監視されてでもいるかのように周囲の気配に敏感になっている。身体も小さく震えていたが、やがて千春の膝の辺りに視線をやるとようやく落ち着いたようにそれは止まった。 「それが気のせいではないと確信したのがちょうどふた月くらい前のことです。塾の帰り――夜の十時くらいです、人気のない道で誰かがついてくる気配がして。足音も聞こえました。私こわくて、しばらくは気づかないふりをしていたんですが、家の近くまで来てから勇気を出して振り返ってみたんです。そうしたらさっと黒い人影が道の陰に隠れるのが見えました」 「顔は」 「見ていません。背が高くてやせていたのは確かですが、顔までは」 「じゃ、どうしてそれがこの……三崎さんだって分かったの?」 「それは、」 「あいつ以外にいないから。他には考えられないの」 千春がハッキリ言った。怒りが顕になった険のある声だった。 「それだけじゃないんです」 感情的になっている千春の言葉を裏付けようとするかのように鞠枝が言い加える。彼女はこうしていつも千春のフォローをしているのだろう。言葉はなめらかに彼女の口を流れた。先刻のオドオドした様子がふっ切れてその声は信憑性を帯びる。 「その……このところはそういう、尾けられているって感覚がパッタリやんで、人影をみることもなくなりました。でも先日、自宅のポストに私宛の封筒が投函されていて」 そこで一旦言葉が切られると、鞠枝の横で千春は苦い顔をした。いまいましげに眉間へ皺を寄せ、口をへの字に結ぶ。その様子をちらりと見て鞠枝は苦笑する。そして膝の上で力んでいた千春の握りこぶしをポンポンと軽く叩いてから、ため息のような声で言った。 「写真が、入っていたんですよ……」 「写真?」 「私が写っている写真です」 「げえ」 「それも外を歩いているようなのじゃないんです。自室で、着替えをしているところを写したようなものばかりで……」 「げええ」 りん子が心底気味悪がっていると芥辺は短く、それから、と先を促す。彼はとても静かで、何を考えているのかまるで分からなかった。 「そのなかに一枚だけ覚えのある写真が紛れていたんです。ただの風景写真だったんですけど、確かに以前三崎先生に見せてもらったことのあるものでした。それでびっくりして、千春ちゃんに相談したんです。そしたらこの事務所の噂を聞いたものですから、行こうってことになって」 「今に至ると」 「ハイ……」 ふう、と鞠枝は息をついた。先ほどりん子が出したアイスティーのグラス、水滴が周りに浮かびはじめているそれを持ち上げてストローをくわえ、こくんと一口飲み込む。ずいぶんとたおやかな動作なのでりん子はついつい凝視してしまう。 「でもこういうのって、やっぱり警察とかに相談したほうがいいんじゃないですか」 これは彼女たちと、同時に芥辺に向かって同意を求めた言葉だった。想像していたよりもずっと”まっとう”なストーカーのようなので、こんな胡散臭い探偵事務所なんかに相談している場合ではないのではないかと思ったのだ。 しかしこれに答えた千春の声はますます怒り心頭といった様子だった。血がのぼって赤くなった頬を衒いながらいくらかヒステリックに言う。 「警察なら行きました。鞠枝に相談されてすぐ私と二人で。でもまともに取り合ってもらえなかったんですよ、気のせいじゃないのかって言われて、信じてやりたいけど今すぐに動くことはできないって。それで」 「写真を見せろ、って……」 繋いだのは鞠枝だ。うつむいて沈んだ声は絶望に濡れていた。 「信じられない。どういう神経してんだろ。着替えてるとこだって言ってるのにそれを見せろって言うんですよ? 結局パトロールを強化する、十分に注意するからまた何かあったらきてくれって。バッカじゃないの、何かあってからじゃ遅いっての!」 ほとんど叫ぶように言った千春の肩をやさしく宥めるように鞠枝は撫でた。被害者は鞠枝のはずだったが、これではどうにも千春のほうが当事者のような感じだ。赤くなった目からは今にも涙がこぼれそうでりん子はふいに切なくなる。 「話は分かった。要はこの男のストーキング行為をやめさせてほしいということだな」 そんな美しい情景にはちっとも気がつかないように芥辺は要領よくまとめた。千春はむっとして、 「それだけじゃ足りない。捕まえて懲らしめて二度とこんなこと出来ないようにしてやりたい」 と恨みのこもった声で言った。 「お金なら払います。いくらだって」 「でも、高校生でしょ。いくらでもって言ったって」 千春は鞄の中へ乱暴に手を突っ込むとがしゃがしゃとかき回して一通の通帳を取り出し、バンッとテーブルに叩きつける。そして、これでも足りませんか、と詰問口調で言った。 「ちょ、これ……」 開かれた通帳のページには機械でプリントされた素っ気ない数字が並んでいる。一番最新の日付は昨日になっていて、その金額は。 「ひゃ、ひゃくまん!」 間違いない。何度数え直しても、1と書かれたあとに続いて0が六つ。百万、だった。 「どうしたのこれ」 「高校進学を機に、父が私の口座に振りこんでくれたお金です。まだ一円も手を付けていません。これを全部支払っても構いません」 りん子は仰天しながらそっと鞠枝を窺った。鞠枝は罰の悪そうな顔をしてうつむいている。たぶん、もう何度も千春を止めようとしたのだろう。そのやりとりが眼に浮かぶようだった。 「やっていただけますか」 するどい目をして、千春は睨むように芥辺を見た。友情ってすごいなあとりん子はよく分からない焦りを感じている。感心しようにも理解の範疇を超えすぎている。百万、百万、と頭の中だけで反芻して、それでも足りない自分の借金について考え目眩すら覚えたのだった。 「そこまで言うのなら」 芥辺は一度ため息をついてから諦めたように、それでいて咎めるように千春を見た。 「その代わり一切をこちらに任せ、絶対に手出しはしないでください。それを約束していただけるなら依頼をお受けしましょう」 突然丁寧になった芥辺の口調はふたりをクライアントと認めたしるしだった。そうと知らず面食らって、慇懃な態度に千春は一瞬怯むそぶりを見せる。しかしすぐさま顎を引いて、 「約束します。必ずあいつを取っ捕まえて再起不能にしてやってください」 と強く言うのだった。 「千春ちゃん」 探偵事務所を後にして表の通りまでやってきたとき、鞠枝は静かに千春を呼んだ。 「よかったね鞠枝。これでもうあいつに苦しめられることもないよ」 千春は鞠枝をふり返って嬉しそうにそういった。 表通りには人も車も来たときよりずっと多くなっている。帰宅途中であるらしい地元の中学生らは晴れ晴れとした顔で笑いながらふたりを通り過ぎる。喫茶店やファーストフードの店にも多くの人間が入っていて、ふたりはその喧騒の中にまぎれていた。 陽はようやく、ほとんど分からないくらいの角度で傾きはじめていた。しかしアスファルトから立ちのぼる熱気は相変わらずだった。目に見えそうな暑気が汗を滲ませる。往来の真ん中で立ちどまりその細い身体を行き違う人々の間に隠しながら、鞠枝はすっと千春を見、そして言った。 「千春ちゃん、前にも言ったけどお金のことは私が何とかするから」 千春はおどろいて目を瞠る。きょとんとして二三度またたきをしたかと思うと、けれど鞠枝の思いつめた声音には気づかないようにカラカラとした調子で笑う。 「何いってんの。良いって言ってるでしょう。どうせ使うあてもないんだから、全部鞠枝に使って、」 「いらない!」 突然荒らげられた声に周囲の人々がちらちらと視線をやった。鞠枝が強く反駁したことに、千春は少なからず動揺する。 「自分で何とかできる。千春ちゃんにそこまでしてもらわなくたってだいじょうぶよ」 「なにそれ、迷惑ってこと?」 千春の声がふるえる。鞠枝はようやく千春の目を見、それから悲しそうにうつむいた。 「そういうことじゃないよ。でも……私、何にも出来ない子供じゃないの。千春ちゃんにそういうふうに思われるのは、イヤ」 「わ、私はそんなこと思ってない!」 「とにかく何とかするから。ここまで付き合ってくれてありがとう」 めずらしく、鞠枝はハッキリと言葉を切った。ありがとうとは言ったものの、それはすなわち、もういいよ、という意味の言葉だった。 「鞠枝、」 「先に帰って。私は塾があるから」 千春はそれから二三度、口を開き、閉じるのをくり返した。何かを言おうとして、でも言えない。鞠枝はついに顔をあげることもなく、かたくなにそこから動こうとはしなかった。 「……ッ!」 千春の動揺が強く伝わってくる。次の瞬間、彼女は長いポニーテールを揺らしてかけ出していた。 それでも鞠枝は追いかけない。日差しに包まれた白い体が溶けていきそうに、陽炎に揺れる。 「鞠枝ちゃん」 りん子が声をかけると、鞠枝は弾かれたように顔を上げた。 「あ、佐隈さん……」 暑気に当てられたのかそれともべつの何かによるものかその表情は血の気が失せていっそう白く見える。瞳は不安げで、その姿は事務所のソファに腰掛けていた彼女とたしかに同じ人物と見えた。強い口調で千春を否定した先程の少女はどこへ行ったのかと思うほど、鞠枝の身体は細くて、やはりはかなげだった。 「変なとこ、見られちゃって……」 鞠枝は目を逸らしごまかすように笑う。 「ううん。あのね、これ、忘れていったでしょう?」 「あ」 「違った?」 「いえ。私のものです、どうもありがとうございます」 礼を言ってりん子の手から、小さなクマのストラップを受け取る。 「鞄につけてたのが取れちゃったんですね」 チェーンを鞄のファスナーに器用にくくり、二三度、いとおしそうに指先で撫でた。 「千春ちゃんは、ずいぶんとあの人を懲らしめてやりたいみたいだねえ」 りん子が言うと鞠枝は苦笑した。 「千春ちゃんは、三崎先生がそういうことをしたっていうのが許せないんですよ」 「どういうこと?」 「千春ちゃん、三崎先生を好きだったんです」 「ええ!? だってあんなボロクソに言ってたのに……」 「好きだったからこそ許せないんですよ。私には分かる。千春ちゃんはいつも行き過ぎるくらい潔癖だから」 そういって鞠枝はすこし目を細める。その横顔はひどくおとなびていた。 りん子は妙にどきどきして、少女の全身を隈なく見遣る。白く透けて病的に思われたその肢体がにわかに艶めかしさを得たような気がし、女子高生ってやっぱ最強だなあ、と今度こそ感動しながら思った。 「鞠枝ちゃんは、あの子が彼のことを好きだって知ってて、付き合ってたの」 「そうですよ。告白されて、断らなかったんです。だって私が千春ちゃんのために、なんて言ったら、ぜったい怒られちゃうもの」 千春ちゃんはいつもそう。鞠枝は悲しそうに言う。 へええ、としか答えることが出来なかった。女の子同士のそういう難しい関係はりん子には覚えのないことだったので、どうすることが正解なのか、想像すらできない。 「でも、千春ちゃんに相談したのは間違いでした」 鞠枝は小さく言うと、また目元に陰をつくった。陽炎でもやもやとしている道の向こうに駆けていった千春の背が見えているように目を細め、それからため息をつく。弱々しい息だった。炎天下の道に車のクラクションが短く、一度だけ鳴った。 「戻りましたー。いやあ、外はほんとあついですねえ……」 表に出ていたのはほんの一瞬だったというのにりん子は首筋や背中にしっかりと汗をかいていた。冷房の風が余計に冷たく感じられてぶるっと身体をふるわせる。キッチンへ行き、冷蔵庫を開けるとそのなかから麦茶を取り出してごくごくと飲んだ。逃げていった水分を補うとりん子はぼんやり、先程のやりとりを思い出した。 「どうかしたのか」 ぼうっとつっ立っているりん子を訝しんで、あるいは気遣って、芥辺が短く声をかける。 「いや、うーん。今日日の女子高生のことはよくわかんないなあと思いまして」 「なんだそれは」 「さあ……私にもよく」 芥辺の問いはりん子自身の問いでもあった。あれはなんだったんだろう。考えると、自然とあの鞠枝の横顔が思い出された。ややしてから麦茶の瓶を冷蔵庫に仕舞ってキッチンを出、ソファからデスクチェアに移動していた芥辺に向かって尋ねた。 「依頼、受けるんですか」 芥辺は顔を上げりん子を見る。その表情が曇りがちだったのに気がついたらしく、 「イヤなのか」 と簡単に問うた。 「嫌ってわけじゃないですよ。放っておけないし……でも、こんなカタギっぽくないとことあんまり関わってほしくないなあって」 「依頼は依頼だ。断る理由もない」 素っ気ない返答だった。それゆえに反駁の余地もない。まだ何か言いたげなりん子に向かって、けれど芥辺は意外なことを言った。 「だが、君はこの件には関わるな」 「どうしてですか?」 「どうしてもだ。とにかく今回は俺一人でやる。さくまさんは別の依頼を受けるか、そうでなければ休みをやってもいい」 「えーつまんなーい」 「文句を言うな、上司命令だ」 「ハイハイ」 芥辺の『上司命令』はよく分からないところで発動される。しかし今回はりん子もおとなしく従うことにした。『上司命令』であるならば仕方がない。あの子たちのことは、私にはどうすることもできない。そう思いながらソファに腰掛け、なにか物憂い気持ちになってため息をつく。 「あー、あっついなあ……」 そう呟いて、炎のような太陽と白い建造物のような積乱雲とが遠いところで燃え立っているのを、何ということはない、けれど何か、不確かな予感のようなものを感じながら眺めた。 (続く) |