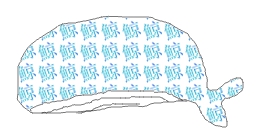 わたしがそれを口にしたのは、折から彼に、夜の雨のにおいを感じていたからだった。 雨上がりの街は濡れた道に反射する様々な灯りで平時よりも明るくなっていた。生温い大気が充満し停滞していた近ごろの夜とは打って変わって、するどく冷やされたその空気をもっと感じたいと思った。夜のにおい。雨のにおい。澄みきった街の、明るんだ道々。 窓を開いて身を乗り出していると、芥辺さんはすこし顔をしかめた。危ないよと素気なく言って自分はさっさとデスクに向かう。キーボードをたたくリズミカルな音が聞こえてきて、わたしは口をとがらせた。なんだ、つまんないの。 今日がいつもと少し違うのは、あのやかましい悪魔たちがいないこと、事務所には芥辺さんとわたしのふたりだけしかいないこと、そして時刻は九時を回り、先程まで降っていた雨がつい今しがた上がったばかりだということ、たったそれだけのことだったのだけれど、わたしは妙に浮かれていた。雨のあとはいつも気分がいい。そういう、習性、みたいなものを持っているのだ。 「アクタベさん。雨のにおいがします。とってもいいにおい」 そうして冗談半分で口にした散歩がてらコンビニでも、という唐突な提案は、しかし意外にも彼に受け入れられたのだった。 「さくまさん、鍵」 「ちょっと待ってください、いま」 バタン、と重たい扉が大袈裟な音を立てて閉まる。鍵をかけるのはわたしだ。 薄汚れた雑居ビルの階段を下りて表へ出ると、窓から感じたそれよりも遥かに濃密な、雨のにおいがそこらじゅうに満ちている。まだ細かい水の粒子がのこっていて、それらはわたしの頬や腕をしっとりと潤した。気分を良くしたわたしが上機嫌で言った、気持ちがいいですね、という言葉は、けれど芥辺さんの賛同を得られないまま行き場をなくし、そうして夜の暗がりに消えていった。 わたしたちは裏通りを選んでコンビニを目指した。この時間のこの辺りはたしかに人も少ないが、同時に街灯の数もうんと少ない。東京の真ん中にもこんなに暗いところが存在するのかと半ば感心しながらわたしは、そうでなければむずかしいほどの執拗さで隣をゆく人の隅々までを見遣った。 芥辺さんのくたびれたスーツは彼を人と街になじませる大切な要素だ。飛びぬけて背が高いわけでもないはずなのに、芥辺さんは人混みの中にあってハッキリとその存在を浮き上がらせる。異質な感じがするのだ。それが何に由来するのかは分からないが、そういうひとって探偵に向いてないんじゃないかなあ、と少し思う。ああだけれどもそういえば、彼が探偵らしい探偵業務を行っているところなどみたことがない。そういう仕事に関しては割合わたしや悪魔たちのほうにお鉢がまわってくるので自覚はあるのかもしれない。 わたしは彼の頭頂から爪先までをつぶさに観察し、やはりどこか溶けきれない彼の違和感がこの夜ばかりはうっとりと和らいでいるのを感じた。そしてそれはどこかでわたしの心を落ち着かなくさせた。だからアクタベさんでもコンビニなんて行くんですね、なんて軽口をたたき、気を紛らわせる。ちらと彼をうかがうとうっかり視線がぶつかったので、慌てて知らぬふりをした。 「明日は晴れますかねー」 暢気な調子は半分が演技だ。けれどそうしてみるとすんなり心は平静を取り戻し、上空を仰いで雲行きをたしかめるほどには余裕が生まれた。月が綺麗だった。そうだ、わたしはコンビニへいくんだ、アクタベさんがなんだと、変に強気になって両腕をぶんぶん振りながら歩く。 そうしてコンビニまでの決して長くはない道中で気付けばわたしは疲弊しているのだった。 ありがとうございましたー、と間延びした声が自動ドアの閉まる動作を追いかけて背中にぶつかる。外へ出ると冷えた空気がいっきに全身をつつみこみ、わたしは一度小さく身ぶるいをした。 ポリエチレンの白い袋が音を立て、提げた右手からぶらぶら揺れる。中に入ったグリーンティのハーゲンダッツが目に入るたび輝いて見える。はやくわたしに食べられたいと言っている。気がする。わたしもはやく、食べてあげたい。 「……」 わたしは来るときに一度そうしたように、ちらり、と芥辺さんをうかがった。芥辺さんは鋭利なかんじがするのにしなだれる緑のようにしっとりしている。夜の雨のにおい。じっと見詰めていても、今度は視線はぶつからなかった。パタパタという足音と、夜に溶けてしまいそうな彼の姿がそこにある。確かな足取りでわたしの横を歩いている。 「本当に、」 意を決して口をひらいても大した話題は思い浮かばない。わたしは手の中の袋を握り直し、努めて自然に聞こえるように声をあらわした。 「なにもいらなかったんですか?」 「うん」 街灯がスポットライトのようにわたしたちを照らしている。力の抜けた歩き方をするので足音がすこしばかり妙だ。 「なんだか付き合わせちゃったみたいで、すみません」 「ああ」 ああって、なんだろう。わたしはすこし不満げに眉根を寄せた。そしてふたたび沈黙が訪れたことに落胆し、また安堵しているのだった。 芥辺さんは結局、何にも興味を示しすらしないでコンビニを出た。 夜のコンビニと芥辺さん、それは、意外にもよくなじんでいたように思う。暗闇にぼっと灯るおびただしいほどの蛍光灯の明りを背にした、彼のたたずまいは正しい感じがした。コンビニとか、けっこう、来るのかもしれない。そう思ったくらいだった。 だから芥辺さんが何も買わずに出て行こうとしたときには思わず引き留めてしまったのだ。なにも買わないんですか、と尋ねると、芥辺さんはうんとだけ言った。そしてやはり迷いのない足で帰ろうとわたしを促した。 いらないんですか? いらない。本当に? しつこい。 「……」 でも、それじゃあどうしてついてきてくれたんだろう。ハーゲンダッツと、それから明日喚び出すことになるであろう悪魔たちのお気に入りのスナック菓子を見やりながら考える。(芥辺さんは相変わらず口数が少なくて、だから一緒にいると何がしか思考せずにはいられないのだ。) ああそうだ、芥辺さんも散歩がしたかったのかもしれない。月が綺麗で空気が澄んでいて芥辺さんからは雨のにおいがして。きっと今日はそういう日だから。 わたしはいたずらにふらついて、風のない夜に風を感じるように道を歩いた。 「さくまさんさ」 「はい?」 アスファルトから静かに立ち上ってくる冷えた空気が少しばかり肌寒く感じられるようになったころ、そしてそれは事務所まであとほんの一分の距離も残ってはいないというころ、芥辺さんが突然口を開いたのでわたしは間の抜けた声をあげた。それを聞いた芥辺さんはちょっと呆れたように間を置いて無表情でわたしを見つめていたけれど、やがてふっと息を吐きだしたかと思うと、言葉をつづけた。 「さくまさんは、天国とか地獄とかって、信じてるか」 「……はい?」 何を言い出すんだ、この人は。 わたしは少し考えるふうを装って開いているほうの指で髪先をいじり、うーん、ともっともらしく唸ってから言った。 「信じるもなにも。悪魔とか天使とか、そんなものをこれだけ見せつけられて疑うほうが難しいですよね。まあ実をいうとアザゼルさんたちが悪魔だってことすら半信半疑なんですけど、役立たずだし」 「悪魔がいるのは地獄ではないよ」 「あれ? そうなんですか?」 「……質問を変えよう。君は、自分が死んだらどうなると思う」 「わたしが、死んだら?」 パシャ、と水溜りを踏んだ。足元を見るとそれは暗い鏡のように光っていた。アスファルトの色を吸って真黒に澱んでいる水は深さにして指先ほどもありはしない。それなのに何故だか底なしの深淵のように、どこか途方もない場所へ続く入口のように不穏で、わたしは慌てて足を引き抜いた。 「どうって、それは……えと、魂? とか、そういうのが、あ、そうか天国、天国へ行って、それから、ええと……」 「すべての人間が、天国へ行ける?」 「それは、どうでしょう……」 芥辺さんの言わんとしていることが分からなかった。こういう身のない問答はいかにも嫌いそうなのに。からかうような声音も馬鹿にしたような含みもたくらみのような不穏さもない。天国って信じてる? そういう純粋な問いかけ。 君は死んだら、どこへいくの? 「さくまさんは天国へ行けるかな」 「どーゆー意味ですか」 「そのままの」 「そんなの分かりませんよ」 「そうか、分からないか。悪魔使いの佐隈りん子さん?」 「……」 なんて性質の悪い。わたしは胸中で毒づいた。君は地獄に落ちるよと、そう言いたいんだろうか。一体誰のせいだと思っているのだ。わたしが地獄に落ちるとして、それが悪魔使いであるが故だとして。一体誰のせいだと。腹が立ってたまらず、 「だったらアクタベさんも地獄行き決定ですね」 と肩をいからせて言うと、 「うん、そうだな」 と、けれど芥辺さんはそんなふうに事もなく答えるのだった。 この瞬間、芥辺さんが笑ったように見えたのは、多分気のせいだったと思う。道は相変わらず暗かったし、わたしは目が良くはないし、だからそんなふうにありもしないものを見てしまったりすることだってたまにはあるのだ。芥辺さんがどういうつもりでこんな話をはじめたのかも、どういうつもりで、そうだな、などと答えたのかも、またどういうつもりで、わたしとふたりこの道を歩くことにしたのかも、本当に、これっぽっちも、その意味なんか解るはずがない。 わたしはため息をつきながら、わたしが死んだら、ということをもう一度考えた。死後の世界など本当に存在するのだろうか。死してなお、苦しまねばならぬほど許しがたい罪など、存在するのだろうか。 「分かりませんよ、そんなの」 ……けれどたしかにわたしは悪魔使いだ。そうしていくつか、不幸に触れた。 なんとはなしに空を仰ぐとそこにはやはり、ぽっかりと月が浮かんでいる。やはり綺麗で、やはりひとつきりだ。 死んだあとのことなんて、それはすこしも分からない。けれどたぶんわたしは、この場所にいるかぎり幸福などというものとは縁遠くなって、いつか世界に棄てられるみたいにぐちゃぐちゃになって惨めに死んでしまうだろう。手も足も千々に消え去りヒトであったことすら分からなくなって、誰にも悲しまれることもなく、喜ばれることもなく、ただただ死ぬだろう。 わたしは目蓋をとじた。天国も地獄もわからない。神も仏もわからない。けれどわたしはわたしの死を、たやすく描くことができるのだ。 でもそうしたら。わたしが死んだら、千々になって消え去ってしまったら。ようやくわたしは解放されるのだろう。そういう予感もまた、確かにあった。生を持った肉体でなくなってはじめてわたしは自由になる。あらゆる呪縛、あらゆる規範から赦されて、彼を呪うことも、たとえば愛することも、決して禁じられることはない。 そういうことを、芥辺さんはもしかしたら知っているのかもしれない。 「アクタベさん、」 だからわたしは呼んだ。まだ縛られたままの不自由な言葉だけで、暗い道にぽっかりと、何も残さぬようにただ呼んだ。 「なに」 芥辺さんの短い返答。それは井戸の底から聞こえてくるみたいな孤独な声だった。 ああ、わたしはコンビニへいってアイスを買って夜の散歩をして。ただそれだけのつもりだったのに。 「……わたし、自分が死んだそのあとに、暗いところへ行かなければならなかったとしても……」 「うん」 「それは、もういいです。仕方ないって思います。だから大丈夫です」 胸を張って言うわたしを背に芥辺さんは、ちょっとだけ間をおいて。 「……そうか」 すこし丸まった背中の向こうで今度こそ、笑った。それは絶対に、聞き間違いなんかではなかった。でもそれがどういう笑いだったのか。どうして笑ったのか。わたしの前で笑ったのなんて初めてなのではないのか。そういう一切のことは、ほんのわずか肩をすくめてさっさと歩いて行ってしまった芥辺さんにまるごと攫われて、答えをもらうことがないまま、見えなくなってしまったのだった。 ……そしてまぶしいくらいの、月を見る。 この人の孤独に引きずりこまれたわたしは、なんてかわいそう。ひとつの罪もおかさないまま裁かれて不幸になるのに、やっぱり彼は、泣いてなんてくれないだろう。悪魔みたいに冷たくて、ひんやりしていて、それなのにどうして、触れていたいと思うんだろう。 芥辺さんはついに何も言わなかった。えっちらおっちら、坂道をゆくわたしたちの姿は夜の中にこそふさわしい。 わたしはとうとつ悲しみにおかされて、永遠に伝わることのない弱さで彼のシャツの裾をにぎっていた。やわらかくよれたその手触りがどうしてか温もっていて、ああ孤独だと、もう一度思った。 「行こう、さくまさん」 振り返ることもないまま芥辺さんは言う。 月の光が濡れたアスファルトに反射して、どこまでもつづき、いつの間にか闇へと滲み溶けこんでいる一本の川のようにかがやいていた。ふと後ろを振り返るとそこへはうすぼけた二本の影が伸びて揺れている。それが光の加減で時折、本当はそうでないのに、ふれあうみたいに重なる瞬間が確かに存在するのだった。 わたしはそれをじっと見てから、前を向き彼から指を離す。音を立てるコンビニ袋を持ちかえて半歩前をゆく芥辺さんの横へと並んだ。そして芥辺さんのふらふらした足取りをすぐ隣に感じながらそれでも、やはりどんな言葉も、口にすることは出来なかった。 ◆◇◆◇ わたしたちの舟が漂流し、いかなる岸へも辿りつけぬまま息絶えるとき、わたしにはようやく名が与えられるだろう。彼が自らの孤独を深く刻みつけてゆくために叫ぶわたしだけの名が生を帯びるなら、それは決してわたしを孤独にはしない。わたしは満ち足りて水の底へ沈み、その滓となって永遠に、碧く、青くかがやきつづける。そうしていつしか、彼をとりまく孤独のすべてがわたしになってしまうのならば、これほど幸福なことはない。 この世界のどこにも、ありはしないのだ。 |